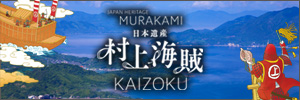本文
2025(令和7)年2月定例市長記者会見
2025(令和7)年2月定例市長記者会見
会見日:2025(令和7)年2月13日(木曜日)
会見内容
1. 令和7年度当初予算(案)の概要について
会見録
【令和7年度当初予算(案)の概要について】
(市長)皆さん、おはようございます。本日は新年度予算の内示ということでご出席いただきまして、大変ありがとうございます。令和7年度の当初予算の概要に沿って説明をさせていただきます。よろしくお願いします。
まず、1ページに予算編成の基本的な考えを掲げておりますが、令和7年3月には御調町、向島町、そして来年1月に因島市、瀬戸田町と合併して20年を迎えます。合併以降、将来を見据えて地域の個性を活かした均衡ある発展と安全・安心確保のため、旧合併特例事業債を活用し、庁舎あるいは消防庁舎整備や学校の耐震改修、道路ネットワークの整備等を進めてまいりましたが、令和7年度は、合併20年の節目という年になると捉えています。市の花、また木が桜でありますので、5枚の花びらで美しい一つの花となるように合併した2市3町が一体となり、「さくら尾道プロジェクト」として、未来へ結びつながるまちづくり、Reborn尾道を目指して予算の編成をしてきたところでございます。
予算編成にあたりましては、諸物価の高騰や人件費の上昇が継続する中、新市建設計画の最終年度において、合併後のまちづくりの総仕上げに取り組むための投資的経費が増加することなどにより、大変厳しい財政運営となりますが、限られた予算の重点化を進めるとともに、有利な起債の活用や特定目的基金の取り崩し等で対応しております。また、令和6年度国の補正予算を有効に活用することにし、令和6年度2月補正予算では、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、生活者・事業者を支援するための事業の追加をお願いしておりますが、公共交通の利用促進事業、尾道季節の地魚の店認定事業、中小事業者の生産性向上等支援事業、学校給食食材費高騰対策事業等、一部の事業を繰越し、令和7年度予算と一体的に実施してまいりたいと考えております。
新年度の新規事業、特徴ある取組につきまして、出産・子育て応援関連では、子育てに関わる負担の軽減や、伴走型相談支援体制の充実など、これまで取り組んできた政策を継続するとともに、「こどもまんなか尾道」をスローガンに、子ども・若者のウェルビーイングの実現を目指して、子育て環境の充実に取り組んでまいります。令和7年度から、保育料の第2子以降無償化が通年化いたしますほか、フードパントリーの増設支援、子育て支援サブサイトの開設に取り組み、産後ケア事業では、産後1年以内の全産婦を対象として、本人負担の無い短時間の日帰り型・訪問型の産後ケアを必要とする方に1回提供できるよう、事業を拡充してまいります。また、令和8年4月の開園に向け、(仮称)北部認定こども園の整備を進めてまいります。
教育環境の充実に向けましては、令和7年4月に尾道みなと小学校・中学校が小中一貫教育校として開校いたします。新校舎につきましては、令和9年4月の供用開始に向けて整備を進めてまいります。学校給食に関しましては、給食費の収納・管理と食材の調達を市が直接行うことで、教職員の業務負担を軽減し、授業改善や児童・生徒と向き合う時間の確保を図るとともに、令和8年度からの市内中学校の全員給食開始に向け、(仮称)尾道地区学校給食センターの整備を進めてまいります。また、英語教育や学校図書の充実を図るほか、市独自の校内教育支援センターを設置し、授業アシスタントの配置を拡充するとともに、不登校や不登校傾向の児童生徒への支援に取り組んでまいります。
安全・安心のまちづくりでは、消防通信指令システムの全面更新に着手するほか、ウェブ版ハザードマップの改修等、防災力の維持・向上に引き続き努めて参ります。
また、地震による建物倒壊等を防止するため、旧耐震基準の木造住宅の耐震改修等の支援を継続するとともに、不特定多数の利用がある大規模建築物の耐震改修も支援してまいります。立地適正化につきましては、居住と都市機能が確保された拠点を軸としながら、拠点間を結ぶ交通のネットワーク化など、多極ネットワーク型のコンパクトなまちづくりの実現に向けて、計画作成に引き続き取り組んでまいります。また、スポーツタウン尾道の推進では、すべての市民の皆様がスポーツに関わる機会を増やすことで、心身の健全な発達や体力の保持増進による健康づくりを図ってまいります。県立びんご運動公園では、令和8年3月に陸上競技場の電光掲示板がリニューアル、4月にスケートボード等のアーバンスポーツ施設の供用開始が予定されており、市ではアーバンスポーツ施設の整備を支援してまいります。
令和8年度には向島運動公園多目的グラウンドの人工芝整備を予定しており、アマチュアスポーツの聖地化に向けて、引き続き各種施策を計画的に推進してまいります。令和7年度も引き続き、出産・子育て応援をさらに充実させるとともに、子どもたちの学びの環境を整えることで、安心して子どもを産み育てることができる環境の充実に全力で取り組んでまいります。
尾道オリジナルの資源を最大化する営みとして従来から取り組んでまいりましたが、すべての市民の皆様が心身ともに健やかで、人とのつながりのなかで心豊かに幸せを感じ、自分らしく輝ける尾道を実現するため、ウェルビーイングの視点を取り入れたまちづくりを継続し、新たな発展に向けたステップの年としてまいりたいと考えております。
続いて、各会計の予算規模でございます。概要の4ページをご覧ください。一般会計は675億円で対前年度比5.1%、32億9,000万円の増額で、過去最大の予算規模となっております。また、特別会計では、8会計の合計が336億3,914万6,000円で、対前年度比3.4%、11億7,049万円の減額となっております。企業会計を3企業合わせまして、264億8,263万2,000円で、対前年度比2.4%、6億1,859万8,000円の増額となっております。なお、市民病院建設に関連する予算につきましては、厳しい経営状況を考慮する中で、令和7年度当初予算案においては、計上を見送ることといたしました。今後、安定経営に向けた経営改善をより一層積極的に進め、できるだけ早期に事業着手に向けた環境を整えてまいりたいと考えております。全会計を合わせますと、1,276億 2,177万8,000円で、対前年度比2.2%、27億3,810万8,000円の増額となっております。
次に8ページの表をご覧ください。義務的経費では、人件費が2.5%減少しております。これは、地域手当の改正等による増額があるものの、段階的な定年引上げによる退職手当の減額等によるものでございます。扶助費では、児童手当給付費や自立支援給付費等の増額があるものの、定額減税補足給付金、物価高騰重点支援臨時給付金等の減額により2.2%の減額、公債費では4.4%の減額となり、義務的経費全体では2.8%、約9億7,300万円の減額となっております。投資的経費につきましては、尾道みなと小学校・中学校、(仮称)尾道地区学校給食センター、(仮称)北部認定こども園の整備費の増額等により、36.3%約22億400万円の増額となっております。投融資関係につきましては、地域福祉基金積立金の増額等により5.3%、約3億4,200万円の増額となっております。
その他では、学校給食の公会計化等により、物件費7.7%、約7億1,200万円の増額、病院事業会計負担金の増額等により、補助費等が14.5%、約10億5,100万円の増額となっております。
21ページから施策体系別の概要及び個別の事業等を掲載しております。これまでご説明いたしました事業のほか、主なものについてのみ申し上げます。最初に「活力ある産業が育つまち」でございますが、農林業関係では、農地の保全に向けた小規模農業基盤整備事業、農道・排水路等の改修事業や遊水池の浚渫に継続して取り組み、中山間地域から島しょ部まで、防災機能含め、持続可能で質の高い営農環境の整備に取り組んでまいります。
有害鳥獣農業被害対策では、広島県鳥獣対策等地域支援機構から派遣される鳥獣被害対策の専門家と連携し、地域での対策への技術的指導や相談対応を充実させ、イノシシ被害の低減に努めてまいります。水産業関係では、令和6年4月に創設された漁港施設等活用事業制度において、俗に海業(うみぎょう)と言われますが、全国の先進事例の一つとして干汐漁港が設定され、今後、宿泊施設や水産物直売所等の誘致などによる漁業振興、賑わい創出に取り組むため、干汐漁港活用推進計画を策定してまいります。また、商工業関係では市が所有する遊休地のうち、比較的大規模な用地について調査し、開発の可能性を探るとともに、引き続き、地域経済の活性化、雇用の拡大、創業の育成に向けた創業・開業等支援事業やオフィス移転等促進事業、中小企業の運転・設備資金融資、因島技術センター支援事業など、国・県と連携する中で、市内経済の活性化に向けて取り組んでまいります。
次に、「活発な交流と賑わいのあるまち」でございますが、移住定住コンシェルジュによる総合的な移住相談や、就労・移住支援、空き家バンク制度の運営など、地域や関係団体と連携しながら受入・支援体制の充実を継続し、移住・定住の促進、関係人口の拡大を図ります。
観光関係では、レンタサイクル利用者の利便性向上や尾道駅前の賑わい創出に資するため、一般社団法人しまなみジャパンが実施する尾道駅前港湾駐車場内レンタサイクルターミナル及び事務所の尾道駅前再開発ビル1階南側への移転を支援してまいります。しまなみジャパンは、レンタサイクル事業による収益力が着実に伸びており、本市を含む3市町からの負担金については、令和7年度をもって終了いたします。歴史的風致維持向上事業では、引き続き旧尾道市街地及び瀬戸田町の歴史的風致地区内の良好な市街地環境形成のため、道路美装化や景観に配慮した修景整備等を進め、官民が連携して地域の活力維持と賑わいの創出に取り組んでまいります。
次に「心豊かな人材を育むまち」でございますが、尾道教育総合推進計画に基づいた教育活動の推進や、文部科学省GIGAスクール構想に基づき、タブレット端末を活用した情報活用能力の育成を目指してまいります。これらのほか、「ひろしま国際建築祭2025」と連携する建築展の開催、囲碁タイトル戦の招致に向けた取組を進めるとともに、令和9年度の供用開始に向け、(仮称)御調文化会館の整備に取り組んでまいります。
次に、「人と地域が支え合うまち」でございますが、協働のまちづくりを継続して推進するほか、幅広い世代の多種多様な思いを把握し、そのニーズに応じた活動を支援していくため、新たにチャレンジ応援プロジェクトに取り組んでまいります。さらに、誰もが性別にかかわりなく、その可能性を最大限に発揮しながら自分らしく生きることができる社会を目指し、「第3次男女共同参画基本計画」策定に着手してまいります。
次に「市民生活を守る安全のまち」でございますが、防災関係では、ウェブ版ハザードマップの改修や、Jアラート機器の更新のほか、引き続き市民一人ひとりの防災意識の向上に向けた取組を通じ、市民の皆様の生命と財産を守るため、防災力の強化に取り組んでまいります。
ごみ処理関係では、生活環境の保全、公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物処理基本計画を策定してまいります。また、老朽化している廃棄物処理施設の整備につきましては、多額の財政負担が見込まれることから、中長期における持続可能な適正処理を確保していくため、施設の再編・統合も含め、整備のあり方や適正な規模、実施時期等の検討を行うこととしております。道路関係では、市内の主要な拠点を結ぶ道路ネットワークを構築する幹線道路や、日常生活を支える生活道路を計画的に整備してまいります。整備後は、点検とその結果による補修を計画的に行う「予防保全型」の維持管理を行うことで長寿命化を図り、管理・更新費用等のライフサイクルコストの抑制に努めるとともに、道路網の安全性・信頼性を確保してまいります。
常備消防関係では、因島消防署の消防ポンプ自動車、瀬戸田分署の高規格救急自動車を更新するほか、令和9年度の通信指令システムの全面更新に向けた実施設計と車両運用システムの更新を行ってまいります。消防団関係では、引き続き小型動力ポンプ付積載車や、消防団器具庫等を計画的に整備・更新するとともに、消防団員装備品の充実にさらに努めてまいります。
次に「安全な暮らしのあるまち」でございますが、8050問題や貧困、介護といった福祉課題は、複合化、複雑化してきており、本市では、令和2年5月に福祉まるごと相談窓口を開設し、複合化した相談の受付や、課題解決に向けた他機関協働の仕組みづくりを開始しました。これまで地域共生社会の実現に向け、地域、行政、関係機関等が協力し、相談窓口の明確化・ワンストップ化、多機関連携による伴走支援体制、支援者への支援体制、引きこもり支援等を実施してまいりました。令和6年度からは、新たに孤独・孤立対策とも連動した重層的支援体制整備事業を開始し、これまで構築した支援のネットワークを、地域に拡大させる取組を実施しています。引き続き、尾道版地域共生社会の実現に向けて取り組んでまいります。しまなみ海道通行料金の助成につきましては、令和6年度から対象と助成額を拡充いたしましたが、事業を継続し、利用していただくための周知に努めてまいります。高齢者福祉では、高齢者が住み慣れた地域で、元気でいきいきと安心して暮らせるよう、高齢者福祉計画及び第10期介護保険事業計画の策定に向け、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査等を実施してまいります。敬老優待乗車証等交付事業では、利用される方の利便性向上を図るため、おのみちバス株式会社優待乗車証を除く、バス・船・タクシー・入浴・あんま等の利用券を統一し、高齢者本人の選択により利用できるよう変更してまいります。このほか、子ども家庭の総合支援を充実させ、要保護児童に対するきめ細やかな支援と児童虐待防止、ヤングケアラーの支援等に取り組んでまいります。
次に、歳入についてでございますが、6ページをご覧ください。市税では、令和6年度の定額減税約5億円の復元や、個人・法人市民税の増額見込等により、6.5%の増加を見込んでおります。各種交付金では、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金などが増加、地方消費税交付金、地方特例交付金は減少を見込んでおります。普通交付税では、全国総額の増加や令和6年度の交付実績、市税の見込等を踏まえ、前年度比2,000万円増の153億2,000万円を見込み、臨時財政対策債につきましては、制度開設以来、初めて発行しないこととされており、2億円の皆減としました。繰入金では、学校教育施設整備基金、大学施設整備基金等の特定目的基金について、関連事業費に応じて繰入額を増額したことなどにより、35.4%の増加を見込んでおります。
諸収入では、学校給食の公会計化等により、39.3%の増加を見込んでおります。市債につきましては、建設事業費の増加などにより、25.4%の増加を見込んでおります。なお、旧合併特例事業債は、約24億2,900万円発行する予定としており、これにより発行可能額の約484億1,900万円に達します。
以上で、当初予算の概要について説明をさせていただきました。
【質問】
(記者)まず総体的な質問をしたいと思います。過去最高の675億円となって、投資的経費がかさんだということでした。一方で、ソフト事業では新規事業で目を引くものが例年より少ない印象を受けました。この辺り、最初の基本的な考え方の中で、限られた予算の重点化ですとか、限られた財源を効果的、効率的に活用している中での、継続事業も含めてのことだと思いますけど、そのあたりの考え方を改めてお聞きしたい。もう一点は、令和8年度以降、同じように予算がどんどん膨らんでいくのか、それとも本年度がピークとなるのか。そのあたりの長期的な考え方もお聞かせください。
(市長)まず一つはですね、令和7年、8年というのは令和9年から新しい総合計画に基づいた10年間のまちづくりに入るということです。そして令和7年、8年というのは、尾道市にとっては令和7年が節目の年になります。合併を通した20年ということで、特例債が使える事業としては最終年ということでございますので、合併して20年を迎える中で均衡ある発展ということと、今のように東日本大震災を含めて、いわゆる防災、そういった整備も必要になってきますので、この7年度につきましては一定の予算の増額はやむ無しという事で、今回増額という形になっていると思っています。そして、またどの事業も必要な事業ですので、それも早く急がれる事業だと思っていますので、7年、8年というのは、9年に向けての、新しい尾道が生まれ変わる大切な時間としてとらえていますので、このような予算編成になっていると思っています。実際に、ソフト事業という話の中では、例えば新しくフードパントリーの事業を本年度からしながら、市内全域の7カ所ということで、社会福祉協議会、尾道の民間事業者とか個人とか、さまざまな形で支援をいただきながら、地域を上げて共生社会の実現に向けて取組を進めているところですので、特にソフト事業が新規にということではなくて、継続してやりながら、まちづくりとしては方向性は共生、地域共生、それから重層型支援ということで、高齢者の人を含めてその取組は、連携をずっと取り組みをしていますので、それは継続しながら、まちづくりの基盤として取り組んでいきたいと思っています。
(記者)次に個別の質問に移りたいと思います。病院事業に関してです。先ほど厳しい経営状況で経営改善を進めるということもありました。当初予算でも市民病院に3億円、みつぎ病院に3億5,000万だったと思います。基準外繰入が計上されています。つい先週には補正予算で計9億円の基準外繰入の予算が発表されました。この状況、厳しい経営状況と言われましたけど、より具体的にどういうところを改善しなければいけないとお考えですか。
(市長)まず1つはですね、全国の公立病院が、これは直接、総務省の自治財政局長と話をする中で、全国的に病院経営が非常に厳しい状況になっている。そして広島県においては、私は国民健康保険施設診療協議会の会長をしていますけど、本当に中山間地域を含めた病院が、公立の病院・診療所が、どこも経営が厳しい状況だ。このような私達の声は、民間の病院もそうですけど、東京とかはですね、財政力があるので、民間病院も含めて支援するんですが、その一方地方はなかなか財政的にそういったことが難しい状況なので、まずしっかりと病院の状況、現状を国に伝えて地方創生するという話の時に、移住とかいろんなことを言っていますけど、安心して生活できる環境が一番なので、このことについて声をしっかり大にして取組をしていきたいというのが、まず今思ってることの一番です。それからもう一つは、先ほどもあるように、現状としては今の制度の中に安定した経営を目指すということで、それぞれ公立の病院2つと診療所を1つ持っていますので、それは関係者と協力しながら安定した経営になるよう、なかなか外来がですね、コロナの感染拡大後、回復してないという状況が、全部のどこの病院もそういった状況ですので、令和7年度はその意味では非常にいわゆる転換期を迎える。インフルエンザが流行ったり、今のコロナもまた流行ったりとか、外来患者について動向注視しながら、経営改善は関係者共に安定した経営になるよう、それを第1にまず捉えて、令和7年度がスタートしているというふうに思っています。
(記者)市民病院に関しましては、2点の基本計画が出されまして、今回の当初予算では見送りとなりました。この移転計画についても、先ほどできるだけ早期に事業着手に向けた環境を整えてとありましたけど、その概算事業費200億円というのが議会でも疑問の声がありまして。その辺りについて意気込みとしては変わらないのかについて教えてください。(市長)基本的には全く方針は変わっていません。尾道を含めた周辺が、先ほども言いましたように、安定的な生活基盤ができるためには、新たな病院建設は必要だというふうに思っていますので、基本的な方針は変わっていません。ただ、財政的な問題がどうしても出てきますので、今のように答弁させてもらったように、まずは安定的な経営に努める、できるだけ早期に方向としては着手していきたいというふうに思っています。
(記者)次の質問に移ります。尾道みなと小中学校の建設費が計上されました。総事業費を61億円に圧縮するということが昨年7月に教育委員会から示されて、その61億円を総事業費上回るという発表が、昨日予算事前のレクでありました。いくらぐらいになると把握されていますか。
(教育総務部長)ただいまのみなと小中学校の総事業費についてのご質問ですけれども、今現在、実施設計で校舎の建築費を詰めている段階でございます。あの、現在令和7年度に計上したものは、校舎の建築費を見込んだ数字となっておりますので、64億、61億となってくると、それに加えて外構の工事費とかも含まれてまいりますので、そのあたり全体の総事業費に関して、まだ申し上げる段階ではないというふうに思っております。
(記者)いつ頃発表になるかということだけを教えてください。
(教育総務部長)すみません。いつ頃発表できるかというその時期に関しても、実際には校舎の建築が始まり、その後、もう使わない校舎に関しては解体していくとか、その後また外構工事に入っていくということになりますので、ちょっとまだ、いつ頃というところを具体的にはなかなか申し上げにくいと思っております。
(記者)最後の質問に参ります。尾道福屋跡地にしまなみジャパンのレンタサイクル施設が入る件についてです。2階にカプセルホテルが決まりまして、1回がレンタサイクルということで、あまり市民は利用しない施設ということにはなろうかと思います。一方で観光客にとってのメリットは大きいかと思いますけど、この2つがまず入ることについての所感を市長お願いします。
(市長)福屋跡地につきましては、いろんな方の声も聞かせていただいて、いろんな方の事業者と交渉してまいりました。福屋の地下にあったような生鮮食品をする場所が近くにあったらいいなという声がありますので、それを受けながら、本当にたくさんの事業者と交渉してまいりましたが、基本的には、皆さん出店を決断することにはならない。要するに、環境としてその収益性が認められないということになるわけですね。一方、今のような、今まであった福屋の業態とは違った業態ということの中で、地元の事業者の方が、カプセルホテル等を含めた2階のフロアということになりました。そして市民の方の利便性をという声を大切にしながら取り組みをしてまいりましたけど、なかなかそれに見合う形の出店に至らない。その中でしまなみジャパンというレンタサイクル事業をやっている、私が理事長をしていますけど、そこの労働環境ということで、駐車場の地下にあって非常に寒いときは寒風の中で業務をしている。そして、暑いときはクーラーも効かないような環境で仕事をしているので、もともとその環境の改善をしたいということがあるので、それから、3市町の補助金も出さないというような状況まで経営環境がなったので、それでそこの出店ということについて、DMO側としても将来を見据えた形でそこのフロアを全部というわけでございませんので。取組をしたいということになったので、一定程度、職務環境も含めて改善できるということで、私たちの方はこのたび予算計上をさせてもらっているということになると思います。今後ともまだ完全に全てのフロアが契約できているという状況ではないので、これからまたそれぞれ交渉していくということになろうと思いますが、今のようになかなか今の福屋の地下にあった状況であるとか、そういうところにはなかなか事業者の関係では難しい状況だというように思ってください。今後とも、出店に向けて、それぞれ努力していきたいというふうに思っています。
(記者)最後の質問になります。今の件で、レンタサイクル移転の費用7,000万円を全額市が支援すると聞いています。なぜ全額なんでしょうか。
(市長)しまなみジャパンに対して、今治側も、今治市の駅の前に環境整備をしました。それは今治市として環境整備をしているということでございまして、私ども今治市の方と協議をする中で、移転することについては理解できますけど、ただ経費についてはジャパンの経費の中から出すということは、自分たちがジャパンの経費とは別に今治市として環境整備をしたので、今回は尾道市の方が整備をお願いしたいという話がございました。それではということで、ジャパンが持っているお金を使うのではなくて、整備についてはそれぞれの双方の市同士が環境を充実させるという、合意の上で予算計上をさせてもらっているということです。
(記者)ちょっと予算付けがなかったんですけど、合併20年で「さくら尾道プロジェクト」。これは具体的にどういうことをするのかということと、新年度の予算付けがされているんですか。それとどういうまちづくりをやっていくのですか。
(市長)概要版をお持ちですか。この「さくら尾道プロジェクト」というのは、合併して、2市3町が一つの花びらとしてさくらということの中で取り組むということで、今年度取り組む内容は、全部「さくら尾道プロジェクト」の中に入れるという思いで作った予算です。
(記者)全部含めてね。施策が集約されるわけですね。
(市長)そう。未来へ結びつながるまちづくりということで、Rebornというのは生まれ変わるという英語の意味と、もう一つはリボンということで、いろいろなところが繋がる、結びつくというような意味なので、その言葉としては未来へ結びつながるまちづくりというのが思いです。
(記者)全予算ですね。
(市長)はい。
(記者)重なるんですけど、市民病院ですけど、こういった状況で非常に経営的に不安定であると。2月で4億、新年度で3億。あり方委員会で、一応今出されている事業計画がありますよね。市民病院の方も説明している220ぐらいの病床ですか。そういった基本的なものですね。基本計画までいっていない。基本構想的なものをもう一度、市民病院の経営を検討しながら洗い直すということはありますか、ありませんか。管理者としてはどういう風に考えていますか。
(市長)当然、様々な形でケースということですから、柔軟に未来を見据えて見直すことも当然あると思いますので、頑なに、今の案、出した内容を、押し通していくということではないと思っています。
(記者)新年度、7年度に基本設計を描く予定だったんですけど、経営が安定すればそういうことにもなるんでしょうけど、見ていたら病院経営は非常に厳しいわけでしょ。市民病院の経営自体もかなり厳しいというような状況なわけで、今後のスケジュール感はちょっとずれてくる可能性もありますか。
(市長)今回のように予算を上げてないというのは、まずは経営の安定化。できるだけ早期に前に進めていきたいわけですから、方向性は変わりませんけどどのような形で進めていくかというのは、国の診療報酬の改定であるとか全国の病院の状況であるとか、様々な形で、これから地方創生という話をされる中で、地方の病院も診療所も非常に厳しい環境にあるという話なので、その辺りの声を入れながら、新しい方向性を出していただきながら検討することも必要ですので、全体的な見直しをしながらということだろうというふうに思います。
(記者)方向性っていうのは、要するにあり方委員会の計画、基本構想みたいなもんだけど、そういうものも見直していく可能性はある。そうじゃなしに、ある程度一定を維持しながら進めていくのか。
(市長)状況について、検討いうよりか、あり方検討の関係者についても、今の状況を見る中でどのようにするかというのは協議をしてもらいながら、また考えていただくということもあろうかと思いますので、決して今のように出したブラン、これでいこうというような話ではないので、柔軟に当然考えていくべきところは考えていかないといけないと思っているということです。
(記者)福屋ですけど、しまなみジャパンの理事長は市長ですよね。福屋の場所はサイクリングの置き場と事務所だけということでいいですか。どういうふうに活用するんでしょうか。
(市長)まだ1階のフロア全部を、こうしますというところまで至っていませんので。
(記者)だから、しまなみジャパンが借りるのは1階の6割ぐらいを借りてやると。(市長)ですから、それの費用の部分だけを今回予算計上させてもらっていますので。
(記者)7,000万円、何に使うのかよく分からんですよ。
(市長)それはきちっとした形で、改修費用も全部あげてやっていますので、また後、どのようにするか聞いてもらえばいいと思うんですけど、全部のフロアについてこうなりましたというところまで至っていないので、今後とも全部入っていただくように努力して参ります。今の段階ではそこまでしか言えません。
(記者)残り1階の4割はどんなです。
(市長)今そこを聞かれても言える状況にはなっていないので。また埋まった状況になれば、発表させてもらいます。
(記者)最後、地下が陥没したんですけど、いろいろ各地で。上下水道もそういったような点検とかそういったことはやられるんですか。
(上下水道局長)5年に1回の点検というのは、これまでも実施しておりますし、今回、国の方からの調査依頼では、尾道市では対象の管口径はなく、埼玉県のような4m70cmとか、そういった大きい管は本市にはございません。2m以上の管を国の方が調査するようにということがあるんですけど、尾道市では1m35cmというのが最大なんですけど、そういったところは定期的に検査をしておりますし、悪いところを発見したら、その都度補修をしております。なので、目視での点検等もこの前いたしまして、今のところ悪いところは発見できておりません。そういった状況でございます。
(記者)大丈夫なのですね。今のところは。
(上下水道局長)はい。
(記者)しまなみジャパンの移転についてお伺いします。現在の場所から駅前の開発ビルに入ることによって、まちとして今よりどう変わっていくのか、そして地域にとってどのような効果をもたらすと考えていらっしゃいますでしょうか。
(市長)しまなみジャパンとしては、今のように職員の勤務体制が非常に厳しい状況の中で、駐車場の1階の部分ということになりますので、日常的に冷暖房が効かないところでの勤務をずっと余儀なくされていたということがありますので、その意味では、福屋の1階というのは環境としては素晴らしい状況で運営ができる。それでもう一つはですね、自転車でナショナルサイクルルートに選ばれたのが第1号認定がしまなみと、それから琵琶湖とそれから霞ヶ浦のりんりんの3箇所、ナショナルサイクルルートを選ばれた時に、要するに今の環境整備ということで霞ヶ浦のサイクリングの場合は、駅舎の中に今のように自転車ショップとレンタルサイクル、それから宿泊施設を駅の中に構成したという実績がありましたので、それをしまなみジャパンの関係者も知っていますので、今のカプセルホテルさんが入ることによって、自分たちの職場環境を改善するとともにということになると、一体的ないわゆる駅前を含めた賑わいを創出されるということで、まあ非常にウィンウィンでビジネスができるということがあって、それも含めて入っていて。それから、ナショナルサイクルルートとしての魅力を高めることができるというのが、しまなみジャパンとしての考え方だというふうに思っています。ただ、先ほど紹介があったように、今までのように市民を対象にした、福屋さんのような店舗構成に今のようにその出店舗になってないので、それに向けてはあくまでこれからまた事業者の方といろいろ交渉して取組をしていきたいというふうに思っています。以上です。
(記者)残りの部分につきましても、観光の拠点化としていきたいのか、それとも市民にとって身近な何か、お店などの出店を考えているのでしょうか。
(市長)決して観光の拠点ということでなくて、市民の声は聴かせてもらいながらそれに答えるような立場で、出店の事業者と対応しているということですけど、結局ビジネスモデルとしてそのスペースが利用されないと出店の希望がかなわないということになるので、そこはこれからも声を聞かせてもらいながら努力はしますけど、結果としてはどのような形になるかというのがまだ不透明なところがあります。
(記者)自転車のことがたくさん出ているんで、付け加えてお聞きしたいのですが、自転車の組み立て場の問題があったと思うんですが、あれは今回移転する中に入ることになるでしょうか。
(市長)もともと今のしまなみサクラ公園の所へ、組み立て場を含めた建設ということでございましたら、基本的にはそれは断念をさせてもらったというのは、予算と建設にかかるのはあまり大きすぎるということもありますので、組み立て場につきましたら、今のように含めて施設は検討していけたらというふうに思ってます。そして、それができましたら、しまなみサクラ公園にある今の施設は撤去していけるというふうに思っているところです。
以上