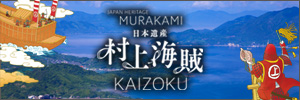本文
2024(令和6)年12月定例市長記者会見
2024(令和6)年12月定例市長記者会見
会見日:2024(令和6)年12月19日(木曜日)
会見内容
1. 「-尾道/山波のアサリ-里海再生プロジェクト」について
2. 「尾道市中学校リーダー研修会の共同制作『尾道かるた』」について
会見録
【「-尾道/山波のアサリ-里海再生プロジェクト」について】
(農林水産課長)「-尾道/山波のアサリ-里海再生プロジェクト」について、記者会見を始めさせていただきます。なお、本日この再生事業の事業主体であります尾道東部漁業協同組合神垣支所長様と当組合の組合員であられますクニヒロ株式会社川崎会長にもお越しいただいております。それでは、はじめに市長の方からご挨拶を申し上げます。
(市長)皆さんおはようございます。先ほど紹介ございましたが、山波のあさりを再生して、豊かな里海を作ろうということで、現在、協力者を、支援者をということでクラウドファンディングで取組をさせていただいています。目標としては、まずは300万円という目標でございますが、現在124名の方に支援をいただきまして、280万円のご支援をいただいているところでございます。目標額まであとわずかでございますが、支援の輪を広げて従来1700t取れていた尾道のあさりが、いわゆる気候変動もあり、今現在3t以下のような状況でございまして、今までも関係者の皆様と共に取り組んできたところでございます。尾道高校の科学部の学生たちも懸命に研究しながら、皆さん方と一緒に再生復活に向けて取り組んでいるということでございます。今日はいわゆるクラウドファンディング等の状況も含めて、東部漁協の皆さんの方から概略の発表をいただきますので、よろしくお願いいたします。
(農林水産課)続きまして尾道東部漁業協同組合方からですねクニヒロ株式会社川崎会長にこのプロジェクトの説明についてよろしくお願いいたします。
(東部漁協川崎クニヒロ会長)おはようございます。今日はこういった、アサリ再生プロジェクトクラウドファンディングのための発表の機会をいただきましてありがとうございます。少し最初は私事になるんですけど、私がアサリ復活の構想を描き始めたのが7年前。そのためにはどうしても漁業権が必要ということで、6年前に尾道東部漁協の山波支所の組合員にさせていただきました。そして、具体的に海に入り始めて干潟の調査整備を始めたのが4年余り前でございます。まず驚いたのが、漁業組合の組合員さん達の年齢が非常に高いということでございました。私が入った6年前、その当時で70歳をもうすでに越えていました。このままでは、いくらアサリを再生復活してと言いながらも、非常に難しいのではないかと直感したわけでございます。そういったことで、これまでも東部漁協さん、いろんな形で市の応援もあって、2012年、13年、14年と3か年にわたり3期に分けて干潟を醸成されております。そこをなんとか守っていきたいと言うのが、東部漁協のまず基本的な考えでございました。非常に恵まれた漁場であって、そこは毎年ですね、種を入れなくても一定の量が採取できるということで、年に5、6回組合の人たちが栽培をして何とか資源を守ってきたというのが、ここ15年、20年の取組であったと思います。ただ、そこからどうやって抜け出してさらなる夢を描いていくかということを考えたわけですけど、私も本業があって、そう時間がとれませんでした。ただ、皆さんが、なぜ70歳にもなってアサリ復活に取り組んだのかということを聞かれます。本当に1980年代、山波の洲はですね、尾道のアサリは瀬戸内海では屈指のアサリの産地でございました。1987、8年ぐらいが一番ピークで、尾道市内で1700t以上のアサリの水揚げがあり、そしてアサリの旬である4月、5月には三次や庄原、府中方面の山間部、そして近隣の市や町からバスを連ねて多くの方たちが潮干狩りに来られていたのが昨日のことのように思います。本当に、子どもから大人まで老若男女が潮干狩りに来て楽しまれていたということで、バケツ一杯ぐらいは皆さんが持って帰られたような記憶がございます。そして我々も皆さんも、尾道の方あるいは尾道近郊の方は覚えておられると思うんですけど、汁茶碗に山盛りに入ったアサリ汁の、味噌汁であったり澄まし汁ですね。白く濁った本当に濃いだしが出て、わたしはそのころから尾道のアサリ、山波のアサリはですね、日本一のあさりだと思っておりました。そして春の朝の風物詩ですけど、アサリ売りのおじさんがおって、アサリアサリいらんか、アサリアサリいらんかということで、その声を聞くのが尾道或いは松永近辺の春の風物詩でありました。ただ残念ながら、1980年代がピークで2000年を越しますと、どんどんどんどん資源が枯渇していって、ここ近年は多い年で4t、少ない年ですと2、3tというのが現実でございます。そういった中で、どういった取組ができるかということで、最初は干潟を小さいところを借りて、どうすれば再生ができるかということで、実証実験ではありませんけど、そういったことを重ねてまいりました。
そのような経験を積む中で、最初はですね今から3年前、広島銀行さんがボランティアとして月一回ですね、干潟整備に携わっていただけるようになりました。ただ、予算的なこともあり、また組合の皆さんが高齢化ということもあって、お金のみならず労働力、これも必要ということで、何ができるかという中でいろいろ声をかけ、広島銀行さんから、あるいは他の団体にも支援の輪が広がっていったのですけど、昨年、東部漁協を中心に、企業そして市民、行政も一体となってですね、「-尾道/山波のアサリ-里海再生プロジェクト」を立ち上げました。昨年そして今年とですね、それが認められて、環境省の令和の里海づくりモデル事業として、国の方から支援をいただきました。金額を言っていいのかどうかわかりませんけど、昨年が500万円、今年が200万円という金額でございます。ただ、これは一つのテーマで連続で支援をして頂けるわけじゃなくて、この500万円、200万円も一生懸命やっとる皆さんが尾道におられるということを認めていただいた中で、2年連続いただいたんですけど、来年は無いものと思っています。そういった中でみんなと協議をして、発想が生まれたのがクラウドファンディングでございます。これを仕掛けられたのは、広島銀行エリアデザイン株式会社の今日リモートで出られている浅野さんでございます。浅野さんも広島銀行さんと一緒にお手伝いをいただいていたんですけど、このクラウドファンディングでお金を集め、そして我々に共感、あるいは賛同いただける若い人たちをもっともっと広げよう、企業にも広げていこう、そして学校、地元の学校にも広げていこう、さらに全国にも広げていこうということで、クラウドファンディングということに辿り着いたわけでございます。内容については、浅野さんあるいは今日オブザーバーとして出られている杉原さんが非常に詳しいですけど、多くのこの取組に協賛頂いた、あるいは賛同いただいた皆さんから、今、市長さんからありましたとうり、現在金額でいえば280万円、そして支援者が124人ということでございます。ということで、最終的な目標はまずは300万円が達成できなければ、この事業は実にならないわけですね。ということで最終的には500万円を目指して、あと残りが1月31日が締め切りということで、12月3日からスタートして今2週間余りが経ったところで280万円ということですから、まだまだ皆さんのご支援、ご協力をいただければ500万円ということ。そしてそのお金だけが目的ではございません。ええ、地域の方々にこういった取組をやっている、そして若い人たちに我々の後を継いでくれる後継者、そういった人にも、呼びかける。そしてブルーカーボン、海の多様性ということとかにも取り組んでいくことが未来のこのアサリ再生に繋がっていくんじゃないかと思っております。ということで、わたくしも自分の人生をすべてかけると言ってはちょっと大げさですけど、そのぐらいの気持ちを持って、このアサリ再生に取り組んでおります。神垣さんが人生をかける、そんなことができるのかと言われたんですけど、僕は自分の退路を断ってですね、こうやって大風呂敷を広げてやっていくのが、わたくしの今までのやり方で、それは市長さんも多分理解をされていると思うんですけど、まずは大風呂敷を広げて、10年先には最低でも100tは水揚げ、今2tですけど、100tにはもって行きたい。そして地元の人たちに、あの白く濁った本当においしいアサリをまずは食べていただきたい。そしてエコツーリズムとか、そういったことで観光の方へも広げていきたい。さらには最終的にはあの山波の洲へ、そして今、我々がやっている東尾道、更には浦崎の方に広げていって、そこにたくさんの人が、本当に我々が子供の時は海に出ている子供たち大人たちがいっぱいいたんですね、山波の洲だけでなくて。それでいろんなものがおりました。手長だこがおったりシャコがおったり、カニがおったり魚がおったり、でもその頃の海と今現在の海ではかなり残念ながら寂しい海になってしまっています。ということで、アサリを再生する、あるいはアマモ増やすということで、多様性に富んだ海をもう一度取り戻したい。そして、なんとしてでも次の世代に今よりはいい形で繋げていきたい。これが強い思いでございます。絶対に途中であきらめるということは絶対いたしません。最後の最後まで、何が成功かわかりませんけど、次の皆さんに喜んでいただく、そして次の世代につなげていく。これはですね、何としてでもやりとげていきたいと思っていますので、皆さんのご支援、ご協力をいただけたら幸いでございます。ということで、一応私からの簡単でございますけど、想いとお願いです。ええ、説明は以上となります。
【質問】
(記者)クラウドファンディングについてなんですが、こちらは目標額に達しなければ全額返金するのでしょうか。それとも入ってきた分は、一応目標に達しなくてもこちらに入ってくるのでしょうか。
(プロジェクト支援者杉原さん)目標額が300万円で今回クラウドファンディングを募集していますけど、杉原です。私がお答えします。あの300万円でスタートしているんですけれども、一応あの目標が達成できなかった時は、オール オア ナッシング方式と言いまして、無かったことになるということになっています。あくまで目標を達成することが大前提のクラウドファンディングことでご理解いただけたらと思います。
(記者)クラウドファンディングの続きですけど、第一目標が300万円、第二目標が500万円ですか。第三目標であるんですけど、今後の展開、アマモを造成したり、干潟を造成したりいろいろあると思うんですけど、今後の展開と今途中経過ですけど改めて途中経過のですね、成果的なものをお願いします。
(東部漁協川崎クニヒロ会長)将来的には。行政の補助金に頼らない形で自走ができる形を作っていきたいと思います。育てたアサリを組合がまずは買い取って、そしてお金に変える。そして市場にも流通させていく、その利益を残していって、それであさりの再生のための資金を調達するということが、最終的にはそうしていきたいと思っています。でも、すぐそれができるわけじゃなくて、その点ではあと2、3年はですね市の方で何とか多少なりとも予算をつけていただきたいと思うんですけど、将来的には自走が自分でできるように、そしてアサリを採って、そして経済効果を生んでということで売る株だけじゃなくて、そこに今度は将来的にはさっきエコツーリズムの話をしたんですけど、観光協会あるいは観光課と組んで干潟で潮干狩りをしたり、そういった形での経済効果も求めて行きたいと思っています。
(記者)それは観光的なものまで含めて展開していきたい、民間の力でということ。
(東部漁協川崎クニヒロ会長)まずはそのアサリをですね、掘ったものを育てて掘ったものをまずは流通さすということ、まずは市内になると思うんですけど、それから備後、広島県内、あるいは県外たくさんできればということで、そういった中でより付加価値の取れる形での出口戦略というものを考えていきたいと思っています。
(記者)あと人材って言うか、ソフト面ですよね。そういったものを担っていく。さっき言われたように。漁業者の方もかなり平均年齢高くなっているし、減ってきていると。その辺も含めて5年先、10年先。10年先に100tぐらい川崎さん目標を出されていますけど、その辺のちょっと。5年先、10年先のちょっと一つ戦略的なものをお願いします。
(東部漁協川崎クニヒロ会長)そのボランティアの人が来られるのは、まあそのたくさんおられれば月一回入ってアサリが育つかといわれたらなかなかそうはいかないですね。今の猛暑であったり、アサリにとって非常に厳しい環境に現在あるわけで、それは少なくとも日々の作物と一緒なんですね。昔はほっといても春になればおいしいアサリが育って、そしてそれを皆さん食べていただいたんですけど、環境がどんどん変わる中で手をかけてやらないと育ちません。農産物と同じように、まずは土地を耕してやる。そして土壌改良のための牡蠣殻の粉砕したものを入れてやる。そして肥料も必要になりますし、そして今度は食害防止のための網張りもいる。ということで、そういった形で、大変な重労働になるんですけど、やはり若い人が必要なんですね。今考えている一つは漁業権というのがあって、非常に難しいんですよ。ボランティアはいいんですけど、じゃあ若い人を集めて、その副業かもわかりませんけど、アサリを一つの生業としてやってくださいというのは非常に難しいです。それで今のところは漁業組合、山波と歌とで今200人ぐらいおってんです。そこ、みんな息子さんもおってんです。その中で、息子さんは職業に就いておられるわけですよ。それで潮の選択がいる、空いている日にそれがいるんですけど、その人たちをリストアップして月に2回ずつ入ってもらう。それをうまく繋げていけば毎週誰かが入っているような形での若返りをたちまちは図っていけば、今の75、6歳の人があと5年も経てば80歳になってしまう。それを繋げていくことはできるんじゃないかと思います。ただ、それは解決したわけではございません。たちまちのところの繋ぎとして、そんな案があるということぐらいに考えていてください。
(記者)川崎さん、さっき10年先の目標を掲げられたんですけども、それよりまだ先の目標になるかもわかんないんですが、他の漁協との連携というんですか、広がりというんですかね。例えば、向島漁業とか。
(東部漁協川崎クニヒロ会長)僕が考えたのはですね、僕がというよりも東部漁協が、まずは小さくても成功体験というか事業モデルを作って、それで上手くいったらそれを広げていきたいということで、松永湾沿いだけでもあと浦崎、松永があるわけですね。それでまあ藤江というこれは福山市になります。そして向島であったり、昔は因島そして瀬戸田でもアサリがたくさん獲れていた。そこも一応実験をしておるんですよ。でも、なかなかうまくいってないですね。種は入れるんだけど、育たない。それは波でさらわれたり、あるいは猛暑で死んだりということなんですね。それでいろんな課題がいっぱいあるんですよ。干潟が少なくなった、あの壊滅的に減ったのが一つ。そして今度は温暖化によって、南の魚特にナルトビエイが入ってきてアサリが大好物なんですね。それが全部食べ尽くしてしまう。もう一つは、海が綺麗になりすぎて栄養がなくてそういったプランクトンがわきにくい。ですから、魚も減っていく。やっぱり海も連鎖があって、植物性プランクトンから動物性プランクトン、それでイリコことかイワシとか小さい魚、チヌとかブリのような中型の魚、それがずっと循環しているんですね。それも切れてしまっているんですよ。今言った三つの大きな課題、これもクリアしていかなければ元には戻らないという中でそう言ったことがあるから、手をかけてやらないとなかなかほっとくだけでは育たないということで、ええ、まずは成功事例を作って、今2年、4年やってきた中でもこうすれば育つというのは僕は見えてきたんですよ。僕がというよりやっている人たちが見えてきた。今の自然採苗ではなかなか不安定で種を採ることできないんですよ。これも人工採苗技術がいるんですけど、そこを手掛けていって安定して種貝を、山波のアサリから取った子ども何百万個か毎年入れていく。今は産卵がうまくできても、その後死ぬ種もたくさんあるんですよ。だから今度は種を人工で採ったものを中間育成して7mmぐらいに育てれば、かなり歩留まりが良くなるんですね。そういったことも必要ですし、IoTとかAIとかいろいろありますけど、そういったことも取り入れてやっていくことがより安定した、そして発展的なアサリ事業につながるんじゃないかなということは考えています。もし広がっていけば、これが浦崎に広がり、因島等の浜とかに広がっていけば、今度300tが見えてくるんです。まず100tですけど。いつまでに300tというのはまだ決めていません。ただ、たちまちのところを100t、その次は200t、300tぐらいまでは多分復活できるんじゃないかなと思っています。その時、私が生きているかどうかはわかりません。
チラシ持たれていますか。QRコードからすべてが見えるんですよ事業内容とか想いとか。新聞とかへは検索してくださいと書いてあるんですけど、QRコードを入れていただいたら一番手っ取り早く支援者に知らしめることができると思うんです。言葉も必要ですけど、できればこれを見たらすべて入っていますという形で記事にして頂いたら助かります。
【尾道市中学校リーダー研修会の共同制作尾道かるたについて】
(教育長)皆さん、こんにちは。教育長の宮本でございます。本市では夢と志を抱き、グローバル社会を生き抜く子どもの育成を目指して子どもたちが自立して主体的に活動し、未来に向けて新たな価値を創造できる力を育むために、本年度は「グローバル、ローカル、尾道らしさ」をキーワードに、様々な教育活動を進めております。その一つとして、市内中学校の生徒会執行部の生徒さんたちに集まっていただき、郷土尾道のために「中学生にできる地域貢献」をテーマにしまして、尾道市中学校リーダー研修会を実施しております。本日紹介させていただくこの「尾道かるた」でございますけれども、昨年度リーダー研修会に集まった生徒たちが企画立案をして、「私たちの町の宝物」というテーマに作成したものでございます。とてもですね、郷土愛そして地域愛に溢れたかるたができました。詳細につきましては、担当の方から説明をさせていただきたいと思います。
(教育指導課長)まず尾道市中学校リーダー研修会についてご説明をします。尾道教育総合推進計画に基づき、子供たちの自主性、主体性を育むとともに、中学校間の交流を図ることによって中学校のリーダーとしての自覚を強め、生徒会活動を連合、発展的なものとするため、毎年2回、尾道市立中学校16校の生徒会執行部の生徒を集め、研修会を実施しております。この研修会では、郷土尾道を愛し貢献しようとする郷土意識を高めることを目的に、生徒たちが郷土尾道のために中学生でできる地域貢献をテーマに様々な活動を計画し、実行してまいりました。これまで実施してきた取組の例としては、市立中学校全校でアルミ缶を回収し、その収益金を使って地域の幼稚園や保育園、認定こども園などに本をプレゼントしたり、中学生が園児に絵本の読み聞かせをしたりする活動などを行ってきました。今回紹介させていただいている尾道かるたは、令和5年度の尾道市中学校リーダー研修会で市立中学校16校で何か共同で作品を製作したいという生徒の声から企画が始まり、各中学校区の自慢を紹介するかるたを作成することとなりました。一つの中学校で3つの絵札と読み札を考案し、今年の11月に完成いたしました。完成した48枚のかるたには、尾道の自然、伝統、文化、歴史、産業、観光、それぞれの分野から尾道の魅力が紹介されており、このかるたを手にした方々に尾道の魅力が伝わることを願っています。では会場後方にも掲示をしておりますが、少し実際のかるたを紹介したいと思います。前のスライドを見てください。これは長江中学校の作品ですけれども、「えーじゃんじゃ 赤のじゅうたん 祭りの声」というかるたです。読み札には簡単な説明もつけたものが作られています。次は「ふ」ですけれども、「振り向けば 自然あふれる むかいひがし」。これは向東中学校の作品です。次は、「や」です。「八千代まで 船作る技 受け継ごう」。これは因島南中学校の作品です。次は、「ん」です。「ん-おいしい 瀬戸田のみかんは 最高だ!」瀬戸田中学校のかるたになっています。このようなかるたが48枚作られているものでございます。ええ、今後は尾道市内の各中学校に4セットずつこの同じかるたを配布し。それを各校の生徒会執行部が活用方法を決め、様々な取組を進めてまいります。以上で尾道市中学校リーダー研修会の共同制作尾道かるたについての説明を終わります。
(記者)まず予算をいくらかけて何セット作りましたでしょうか。
(教育指導課長)予算は21万円で100セットを作りました。
(記者)これは各中学校に配布ということですけど、例えば新聞記事を見て欲しいという希望があった場合には可能でしょうか。
(教育指導課長)今の段階はですね、各校4セットずつ配布して、その4セットをどういう風に使うかというのは、各学校の方にお任せしていますので、ええ、販売というところまでは計画はしておりませんので、そういう声がありましたら、また生徒会執行部の方が考えていくのではないかと思っています。
(記者)最後に、絵がすごく上手ですけど、この絵も中学生の絵ですか。
(教育指導課長)はい、子どもたちがまず自校の地域の自慢となる場所や地域行事などのかるたに紹介したい写真を撮影し、その写真をトレーシングペーパーに書き写して、そして書き写した絵に色えん筆などで色を付けて絵札を完成しております。
(記者)この尾道かるたの製作は初めてということでよろしいですか。
(教育指導課長)はい、この尾道中学校リーダー研修会の中では初めてになります。
(記者)ということは、他に例えば民間ですとか、別の企業さんとかが作られたというような経験はあるのでしょうか。
(教育指導課長)それぞれの各学校で、例えば重井中学校や百島中学校では、学校ごとに、学習のまとめということでその地域のかるたを作っているというような取組を行っているところがあります。
(記者)そうすると、市内全域に共通で配られるかるたとしては、初めてという理解でいいですか。
(教育指導課長)そうですね。尾道市全体のそれぞれの学校の生徒が集まって、みんなで尾道を全体的に紹介するかるたというのは初めてです。
(記者)すみません。他の自治体とかですと、これを全生徒とか全児童とかに配って、よりその郷土愛を高めるというような取り込みをやっているようなところもございますけれども、この各校4セットずつというのは、予算上の問題なのでしょうか。なんか、浸透するという意味で若干少ないなという印象を持つんですけど。
(教育指導課長)予算が21万円で今回作っておりますので、この中学校リーダー研修会がこれまで、例えばアルミ缶で回収したようなお金など、中学校リーダー研修会が持っているお金で作ったということですので、たくさん配るほど作れていないというところです。今後それぞれ学校の方で活用の方は検討していきます。
(記者)市の予算というわけではなくて、リーダー研修会が得たお金から作ったということなんですね。
(教育指導課長)そうです。
(記者)今後の展開なんですけれども、本当にじゃあこれがどうなって、どういうふうに郷土愛を生み出せたらいいなというような、なんか教育委員会の方で狙っているその使い方、効果みたいなのはありますでしょうか。
(教育指導課長)はい、あの子どもたちが、まずこれをどのように使っていくのかというところを考えていくと思いますので、幼稚園とか保育園とか、あるいは公民館というところで広げていくというような計画をしている学校もあると聞いております。また、市としても、市役所の市民スペースでも展示して、広く市民の方にも紹介して行きたいなと思っています。
(記者)今回、100セットということなんですが、64セットは中学校へいくと思うんですが、残りの36セット。先ほど市役所で提示とおっしゃいましたけど、他にどういうところに配置されるのかと、これもしあの欲しいという方が中学校に寄付するから売ってくれと言った時に、売ってもいいものなのかっていうそれを教えていただけますでしょうか。
(教育指導課長)はい、各校に配ったあと、残りのものはまだこちらにあります。今後の展開については、また色々なお声を聞かせていただく中で、リーダー研修会の中でもまた検討して行きたいと思っています。販売ということについては、今後そういう声もありましたら、また検討していくことになるかと思います。
(記者)販売というよりも、この使い道、このかるたの使いかたはご自由にというか、生徒が考えればいいということですけれど、例えばかなり高額な寄付をする方がいて、その代わりにこのかるたが欲しいって言った時に、それを渡すのもいいようにしていらっしゃるということなんでしょうか。その寄付金を元にいろんなことができると思うんですけれど。
(教育指導課長)子どもたちからは、ふるさと納税の返礼金にこれが活用できたらいいのではないかなというような声も上がっておりますので、またあの子ども達といろいろ検討して、また考えていきたいと思っているところです。
(記者)引き戻しかもわかんない、えっとこのリーダー研修会いうのは何人で構成されているんですか。
(教育指導課長)はい、各学校から3名、生徒が来ておりますので、全部で48名の生徒が参加している会となっています。
(記者)えっとそれで、昨年度のリーダー研修会で何かを共同で作りたいっていう話が出て、実際に作ったのは今年度の研修会。そのことにですかね。昨年度どこまでやって今年度はどこからされたのか。
(教育指導課)昨年度、今の高校一年生の代の子ども達が、読み札や絵札の素案を考えるところまでやっております。そして、令和6年度今年度のリーダー研修会の子ども達が先ほど言ったように、トレーシングペーパーに綺麗に写したり、色を付けたりということをやっております。
(記者)2カ年度に渡って作ったという。それが完成したということですね。はい、わかりました。
【その他の質問】
(記者)市民病院の移転計画についてお伺いします。先日、市議会で建設調査特別委員会が設置されました。これまでの質疑でも概算事業費200億円が将来の財政負担になるのではないか、あるいは埋め立て地が震災の心配がないか、そういった声もありました。市長としては、年明け以降も現在の計画で必要性を訴えていく考えでしょうか。
(市長)基本的に、建設について私たちは進めていきたいという基本的な考えは変わりません。議会の方で調査特別委員会というので、さまざまな角度から勉強していただきながら、情報も取っていただきながら、私たちの方はその議会が取り組む内容についても情報提供等をしっかりしていただいて、取組を進めていきたいと思っているところです。
(記者)本年度は因島の民間2病院の統合の決定もありました。そういったことも踏まえまして、市民病院の役割というのはますます大きくなるとお考えですか。
(市長)病院のそれぞれの取り組み方につきましては、国の指針もございますが、基本的にそれぞれの地域の課題を解決していくために、例えば因島の総合病院、いわゆる宿泊施設も含めて耐震強度がないという状況を踏まえながら、最適な医療を取り組んでいくという方向の中で、因島の医師会病院を軸とした取組ということでございますが、圏域としての医療を守っていくということは、もちろん尾道の市民病院は因島のいわゆる医師会病院も瀬戸田の診療所も、今あるJA尾道総合病院、公立みつぎ総合病院、これらをトータルして圏域ということで二次医療圏ですから、当然そういう意味でいうと福山の西部地区のエリアも含めて検討していくということですので、それについては基本的には広島県の考え方も含めて、私どもの方は今のような未来的な思考を含めながら取り組んでいくという考え方で進めていきたいと思っています。
(記者)福本フェリーの件ですけど、来年3月末で廃止ということが決まっております。先日の市議会の答弁の中では、三セクが引き継ぐという考えはないということでした。その点について、改めて現在の考え、福本フェリーの後についての考えを改めてお聞かせください。
(市長)三セクで福本渡船を引き継いでいくという考え方は全くもっていません。ですから、今の三セクのおのみち渡し船株式会社の方で2航路を運行することによって、今後とも今のように利用される方の利便性を取り組んでいきたい。この議会で無償譲渡という形で建造したのも、渡し船会社に譲渡することも承認いただきましたので、その意味でいくと渡し船会社の運行で、これからいろんな関係者とも力を貸していただきながら取組をしていきたい。ですから福本渡船を第三セクターの方にという思いは今のところ持ちあわせていないということです。
(記者)はい、ありがとうございました。議会の方、あるいは市民の方からしますと、あの尾道大橋の渋滞がさらにひどくなるのではないか、あるいは、サイクリストたち、あるいは朝夕の駅前航路ですね、駅前渡船が待ち時間が長くなるのではないかという懸念も上がっています。そして、議会の中では福本渡船を引き継ぐとしたら10億円以上かかる。20億円近くということもありましたけど、それを払ってでも公共交通を維持してほしいという声もよく聞きますけど、改めてになりますけど、そういった思いも踏まえて現時点の気持ちをお願いします。
(市長)私どもの、いわゆる今の渡船は、今までも沢山の経緯の中で取組をしてまいりました。例えば、向東の桑田渡船そして岸本渡船。その前は向島の有井渡船。そのような状況で、民間事業者として取組をされて、経営上の課題がある中で運航を停止したという。尾道大橋が架かって、自動車がそちらを渡るようになって、逆に言うと古い尾道大橋の場合は料金を徴収しないという方針のもと、無料の状態も出てくるということですから、様々な渡船事業者にとっては経営上非常に厳しい環境にありながら、私たちはそれを利用する例えば学生であったり、高齢者の方だったり、車に乗られない方ということで、それぞれの立場で今までも議論を重ねながら取組をしてまいりました。その中で、今の向島の駅前の渡船の運行事業者そのものが継続をするということはもう難しいと言う判断という話の中で第三セクターという方式のなかで運行を継続するということを決断したわけです。第三セクターという話の中で、いわゆる代船も含めますと2隻必要でございますので、そのような対応が今できてないということがあるので、議会の承認をいただいた上で建造して渡し船会社ということで、2航路の体制でやるということで、そのことをお話させていただいた。それで取組をしているということでございますので、今のところ福本渡船は一抹私も利用者の一人ですので、そういう意味では寂しい思いをしていますし、福本渡船の経営状況、内情も充分把握した上で、市としての方向性として、2航路運行にしてという方針に至っているというふうに思っていますので、様々な意見があるのは知っておりますが、そのような形でこれから取組を進めていきたいと思っています。今後、どのような形、交通事情も含めてなるかというのは、そういった実態を把握しながら方法については考えていきたいと思います。
(記者)最後の質問になります。今年一年、尾道市にとってどんな一年でしたか。そして来年はどんなイベントなりが待ち受けていますかについて教えてください。
(市長)今年度はですね、御調町と向島町と合併して20年というある程度節目の年ということと、やっとですね、尾道全体として日常が帰ってきたという一年だったというふうに思います。本年度の予算の当初は新しい時代を開くということで、ウェルビーイングのまちづくりというようなことで、全てに渡って価値を、心地良いとか住みやすいとかご機嫌なとか、様々な形の見直しをしながら、尾道の街づくりを、来年がちょうど尾道としては合併20年の節目になりますので、合併特例債を使ったハード事業等も一応一定の方向性で20年かかって尾道の一体感を醸成してきた節目の年ですので、これを次の年に繋げていきたいと思っています。それが、今のように非常にコロナということの中で非常にしんどい、経済状態も含めてしんどかった状況を乗り越えてきて、日常が帰ってきた一年だったというふうに思っています。その意味では、新しいまち・ひと・しごとという創生ということの中で、2014年から取り組んできたちょうど節目の10年目になる年でもございますので、それぞれ今までやってきた取組を一定の成果を得ながらということで、今のコロナ明けての5年ということの中の節目の年で、日常が帰ってきた一年。さらにこれから加速をしていきたいというように思っているところです。
以上