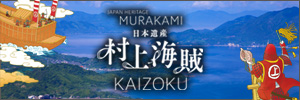本文
2024(令和6)年10月定例市長記者会見
2024(令和6)年10月定例市長記者会見
会見日:2024(令和6)年10月22日(火曜日)
会見内容
1. 「まちかどフードパントリー尾道」の開設について
会見録
【「まちかどフードパントリー尾道」の開設について】
(子育て支援課長)ただいまから、「まちかどフードパントリー尾道」の開設に関する記者会見を行います。私は子育て支援課長の三好です。よろしくお願いします。本日は、「まちかどフードパントリー尾道」の事業主体であります尾道市社会福祉協議会から「くらし支援課」の高橋様にご出席いただいております。はじめに尾道市長平谷祐宏からご挨拶を申し上げます。
(市長)皆様、おはようございます。まちかどフードパントリーという事で、尾道市は初めて取り組む事業でございます。このまちかどフードパントリーというのは、尾道の第三の居場所の取組、学校と就学前の保育所等の環境の中で子どもが十分に食事をとれていないという実態が現実にあります。そういった子供がいるということと合わせて、家庭的に非常にしんどい状況になる家庭があるということがありますので、このたび日本財団の助成を受け社会福祉協議会がまちかどフードパントリーということで取り組むということにしました。実際には、社会福祉法人が取り組むわけですが、尾道と一体となって取り組む。そういった事業をこの度開設して、ここにありますように10月31日にまず1カ所目を取組して、年度内には3カ所程度パントリーを開設予定として現在取り組んでいるところでございます。第1号としては10月31日、尾道市総合福祉センター内に開設するということで、今取組をしているところでございます。一方、その食品等につきましては、民間企業等から寄付をいただくということで、それは食品ロスにつながっていく取組と合わせて、このフードパントリー制度を拡大していきたいと思っています。年度内に3カ所、将来的には尾道全域で7カ所程度想定して、まず今回10月31日に第1号として総合福祉センター内にということでございます。詳細につきましては、担当のほうから説明をさせますのでお願いします。
(子育て支援課)事業概要につきまして、ご説明をさせていただきます。報道発表と書かれた資料をご覧ください。まず、この事業を始める背景といたしましては、本市では子育て家庭からさまざまな相談を受ける中で、充分に食事を取れない子どもや保護者への支援が必要と考え、身近な場所で食品を手に入れることができる仕組みづくりを検討しておりました。この度、尾道市社会福祉協議会が日本財団の助成を受け、まちかどフードパントリー尾道を開設し、本市と一体となって子育て家庭への食の支援と食品ロスの削減を目的に事業を実施いたします。
次に事業概要ですが、地域の企業や個人の方からいただきました食料品等をフードパントリー会場内に陳列をし、事前に登録された利用者が自由に取りに来ることができる事業となります。企業等から提供いただいた食品を保管するため、常温・冷蔵・冷凍のいずれの保管方法にも対応した無人の食品庫「フードパントリー」を今年度中に3カ所に開設する予定としております。この度、その第一号として尾道市社会福祉協議会があります尾道市総合福祉センター内の一室に開設することになりました。残りの2カ所につきましては、総合福祉センターでの運用状況を見ながら順次開設をしていきたいと考えております。私からの説明は以上となります。引き続き尾道市社会福祉協議会から事業内容等についてご説明いたします。
(社会福祉協議会)配布しておりますチラシの表面をご覧ください。はじめに本事業におきまして、食品等をご提供いただける個人や企業の方を「フードパートナー」、パントリーを利用する方を「フードメイト」と呼んでいます。支援をする、されるの垣根をなくし、対等な立場でフードロス対策や食の支援を行い、お互いに支えあう取組になっていくことを目指しております。利用対象者(フードメイ)は児童扶養手当や就学援助を受けられている方のほか生活にお困りの方としており、生活保護受給世帯を除きます。なお、児童手当や就学援助を受給されている方につきましては、個別に文書でお知らせすることとしております。次に、利用の流れとしましては、まず事前にホームページの専用フォームから利用登録をしていただきます。社会福祉協議会において内容を審査しまして、利用可能な方に対しましては、利用に必要なIDとパスワードをお知らせします。フードメイトは公式ラインを使用した専用のアプリにて在庫状況を確認し、パントリー開設時間内であれば好きなタイミングで利用が可能です。なお、利用者の安全に配慮しパントリー入口には電子ロックを設置し、アプリで解除キーを確認して入室していただける仕様となっております。その他アプリでは、入荷状況のお知らせや個人の登録情報などが確認でき、物品の大量入荷があった際には、プッシュ通知でお知らせできる仕組みになっております。このようにフードメイトの方には専用のアプリ一つでフードパントリーが簡単に利用できるよう設計しております。チラシの裏面をご覧ください。図に示しておりますのが「まちかどフードパントリー尾道」の概要となります。フードパートナーから食品等をご提供いただき、社会福祉協議会においてパントリーに陳列し、フードメイトが欲しいものを選んで持ち帰りいただきます。フードパートナーにご提供いただく食品等につきましては、「未開封・未使用のもの」であるとか、「賞味期限・消費期限が2週間以上あるもの」といった一定の条件はあります。ただ、今回パントリーでは、これまでのフードロスの取組の中では、取り扱いの難しかった生鮮食品や冷凍食品も取り扱いができるよう、パントリー内には冷蔵庫・冷凍庫が設置してありますので、野菜、果物、精肉、加工食品や冷凍食品も取り扱いが可能となっております。その他、フード以外にも洗剤やトイレットペーパーなどの日用品につきましても取り扱いを行ってまいります。このようなフードパントリーは4つのポイントで定めまして、これより10月31日より運用をしていく予定としております。なお、パントリーの開設にあたりまして、10月31日木曜日の午前10時から総合福祉センターにおいて、開設除幕式と内覧会を行う予定としておりますので、併せてご案内させていただきます。詳しくはお配りしておりますご案内の文書をご覧ください。以上で説明を終わります。
【質問】
(記者)日本財団の助成を受けたということですけど、この助成の名称ですとか金額を教えてください。
(子育て支援課)日本財団の助成につきましては、特定の名称のある助成ではなく、一般的な社会福祉に関する助成事業になります。本事業は、本市が企画立案をいたしまして、日本財団にこういった内容での助成の方をしていただけないかということで申し込みを致しまして、交付決定を受けたものでございます。助成金額につきましては、本年度は2,174万円の助成金額となっております。
(記者)本市と一体となってとありますけど、市は具体的にどのような役割をはたしますか。
(子育て支援課)今年度、市の方も社会福祉協議会さんに対しまして、補助金を出させていただいています。その他、開設場所の選定であったり、企業さんを訪問してお願いするとか、そういったところにつきましては一緒になってやっております。以上です。
(記者)市の補助金の金額を教えてください。
(子育て支援課)市からの補助金と致しまして、1,300万円を交付しております。
(記者)本年度中に3カ所ということですけど、残り2カ所はもう決まっているのでしょうか。
(子育て支援課)残りの2カ所につきましては、向島と因島にあります公共施設の方に設置をしたいと考えております。
(記者)次に社会福祉協議会さんにお伺いすることになるかもしれませんけど、フードメイト、フードパートナーの現在の登録数を教えてください。
(社会福祉協議会)フードパートナーご寄付を頂く方々につきましては、現在12の企業さんと多くフードパートナー登録を頂いております。フードメイトの方々におきましては、今案内を送らせていただいているところなので現在まだ登録はありませんが、1,100世帯に送らせていただいているところです。
(記者)これまでにフードロスの取組としてフードバンク、フードドライブという取り組みをされていますけど、この内容を始めた時期などについて教えてください。
(社会福祉協議会)フードバンクにつきましては平成28年から始めておりまして、フードドライブにおきましては、はっきり覚えていないんですが、多分令和に入ってからぐらいだと思いますが始めております。
(記者)それぞれの内容とフードパントリーとの違いについて教えてください。
(社会福祉協議会)これまで行ってきたフードバンク・フードドライブとフードパントリー、このフードロスの取組におきましては、今後一体的に取組を行っていく予定としております。従来、フードバンクにおきましては、企業さんから提供いただいた食料品を生活困窮の方に提供する、お渡しをするというような活動させていただいておりました。一方、フードドライブにおきましては、個人の家庭にある食料品を年4回の開催の中でお持ちいただき、基本的には子供食堂にその食材を提供させていただいておりました。このたび、このフードパントリーにおきましては、企業個人問わず一つのパントリーセントラルストレージ中央倉庫のような形でどんな活動にも提供できる食材を集めて、提供先も困窮者、子育て世代、子供食堂含めて提供を行っていくかたちに作り上げていく予定としております。
(記者)また31日にフードドライブがいつから始まったのか教えて頂けたらと思います。
(社会福祉協議会)フードメイトの方につきましては、ラインの公式アプリの中で在庫確認であったりとかが確認できる。まだ正確なものになっていないのですけれども、下の方にある6つのリッチメニューの中に在庫状況が確認できるものであったりとか、各パントリーに納品した際には、このお知らせの方で、こういったものを納品しましたよということが利用者のフードメイトの方に通知できる形を作っております。今回、目指したこととしてフードメイトの方にも公式ラインのアプリ一つで利用が簡単にできるということを目指して作っております。
(記者)3点お尋ねをいたします。この常設型のフードパントリーという取組については県内で何番目かというのがまず一つ目の質問です。これまでそのフードバンク、ドライブですね、単発という形でおやりになっていたと思うのですけれども、この常設でフードパントリーをやるのに、どのような課題があって、どのような課題をクリアしたのかという、そこについて二点目ですね。あと、細かい事ですが、冷凍庫と冷蔵庫のキャパですね。あと、その倉庫全体のキャパがどの程度なのか、そちらも教えてください。以上3点、お願いします。
(子育て支援課長)まず県内で何番目かというところですが、本日の取組と完全に合致しているかどうかわからないですが、神石高原町さんがハローズというスーパーマーケットと提携して開設されているということはお聞きをしております。それから、常設にした場合の課題というところですが、一番大きな課題はやはり場所の問題でございます。県外のさまざまなフードパントリーの形を見る場合に、ずっと食品を保管しておく場所がないからなのか一時的に何月何日の何曜日に何時から何時までフードパントリー開設しますというような形で、店舗であるとか公共機関であるとか、あの一時的な開設というのはされてるところ結構多いんですけれども、ずっと食品を提供する場として確保するところが難しいところでございました。本市においては、先ほど市と一体となってという部分でも説明させていただいたんですが、本市の公共施設を活用するというところで調節型を可能としたというところでございます。それから、キャパシティの問題ですけれども、こちらも、場所によってそれぞれ大きさも変わってくると思うんですが、冷蔵庫、冷蔵庫につきましては、業務用の冷蔵庫、冷凍庫の方を予定しておりますので、ちょっと厳密な容量はわからないですが、業務用の冷蔵庫ですので、一般の家庭用とはちょっと違い、かなり容量は大きいものを予定しておりますで、パントリー自体の広さは、約20平方メートルの広さを予定しております。以上でございます。
(記者)また31日の日に、冷蔵庫と冷凍庫の容量も教えていただければと思います。よろしくお願いします。
(市長)さっき説明があったんですけど、この内容そのものを私どもも日本財団の方と話をさせてもらう中で、取組そのものが非常に意味のある取組になるのではないかということと、今のような形で若い保護者の方という話になると、就学年齢という話になると今、うちもオンラインでやっているんですけど、スマホ持っていることは100%のような状況でございますので、それでラインを使って取組をするといったようなところからすると、非常にこの取組は評価ができる。一方、第三の居場所の取組ということも含めて、連携させてもらった事業として実のある形で、一号をまず開設をして、それから様子を見ながら順次充実させていきたいというふうに今思っているとこです。また現場を見ていただければというふうに思います。以上です。
(記者)こちらの開設時間を教えていただきたいのと、神石高原はハローズとか地元のスーパーと提携して安定的に食料品など入荷するみたいですけど、今、地域企業でどこか名前を挙げられるところはありますでしょうか。
(社会福祉協議会)開設時間におきましては、原則9時から5時というふうに思っておりますが、当然、設置しております今回でいうと総合福祉センターの開館時間内であれば、どなたでも利用できるような形での運用を考えております。地元の企業との提携という事ですが、今回のおのみちフードパントリーにおきましても、先程12あるといった企業さんにつきましては、地元企業とも提携・登録をしていただいております。ハローズさんというお名前を頂きましたが、フードバンクの中でも提供していただいておりましたので、同様にいただく予定としております。あとは地元でいうと、JA尾道さんにもご協力いただきまして、お野菜などの提供をいただく予定としております。
(記者)そしたらここもハローズが入るのでしょうか。
(社会福祉協議会)そうですね。ハローズの店舗の方からいただくような形にしております。
(記者)開館時間9時から17時ということなんですが、この総合福祉センターというのは、何時から何時まで空いているのでしょうか。
(社会福祉協議会)総合福祉センターの方が曜日によって開館時間がちょっと異なっております。火曜日、木曜日につきましては、夜間の貸館がある場合は夜9時まで空いておりますので、利用状況によって若干利用できる時間が異なってくるという形になっております。
(記者)今年度は日本財団からも予算・助成金を貰っているということですが、7カ所はいつまでに開設するのでしょうか。その7カ所全部に日本財団の助成がもらえる見込みがあるのでしょうか。
(子育て支援課長)はい、一応3年間の計画で7カ所を実現できればと思っておりまして、財団の助成を受けるのは、もちろん単年度ごとの申し込みが必要ですので、確約をいただいているわけではございませんが、当初の計画としましては3年で7カ所ということで申請をしております。先ほどの開館時間の件なんですけれども、総合福祉センターについては、先ほど高橋が申し上げました通りなんですが、今後公共施設を順次活用して参りますので、場所によってはもう少し長い時間、ご利用いただけるのではないかというふうに考えております。
(記者)あと土曜とか日曜は空いているのでしょうか。
(子育て支援課長)総合福祉センターもですね、土曜、日曜空いてございますのでご利用いただけます。
(記者)こういった食事関係とか、子ども食堂とかいろいろ増えているんですけど、その全体として食事が充分に取れている子どもたちは増えているんですか。いろんな形でいろんなものが出てきているわけですけど、子供あるいは子ども世帯の貧困化が進んでいるんですか。尾道市で。
(子育て支援課)具体的に統計的なものは正直ないのですけれども、先ほど最初の説明でも申しましたが、私どもが家庭児童相談のケースを相談対応をする中とか、保育所、認定こども園の子どもさんの状況であるとか、子ども第三の居場所の利用の中で知る家庭の状況を見ると、食事が充分に摂れていない子供さんは一定数いらっしゃる認識でございます。その食事が摂れないことで、当然体の成長発達にも影響がございますけれども、食事が摂れないばかりに学校の方へ登校ができないであるとか、あとあってはいけないことですけれども、万引きであるとかそういったことに手を染める子どもさんが出てきているという実情は見受けられます。
(記者)難しいと思いますが、現状でどのぐらいですか数字的には。いろんな対応していますよね。今回はパントリーですか、あとフードがあったり、子供食堂があったりするんですけど、どのぐらい食事が難しい貧困家庭があって、それに対応していろんな施策を出しているわけですけど、どの程度対応しているか。パーセントを出すのはちょっと難しいでしょうけど、充分ではないからこういうような施策を追加でうっていってるわけですね。今後もそういうようなことが増えてくるんですか。数字的なものが分かりましたら。大人はいいですから子供だけに限ってどのぐらい。
(子育て支援課)そこを数字で出すっていうのは大変難しいところなんですけれども、調査も直近で行ったのが平成28年になりますので、その時点では子どもの数ではなく、世帯の数としては13%程度のご家庭について充分所得が足りていないんじゃないかっていう調査は一度行いましたけれども、現状では先ほど申し上げました対象世代は1,100程度ということでございます。
(記者)それは、小学校から高校生までですか。
(子育て支援課長)子どもなので高校生までです。
(記者)高校生までの平成27年度は13%ぐらいが非常に食事に困った家庭だというふうに見ていいですか。今この数字は、生活保護世帯とか低所得者の数字。13%は。
(子育て支援課長)あの1100世帯につきましては、児童扶養手当受給世帯、それから就学援助の受給世代の合計でございまして、生活保護の受給者は入っておりません。
(記者)それでも今の施策では足りない。食事の面で子供たちへの供給が足りない。
(市長)何パーセントなんとかって数字の問題ではないんですけど、先ほどあったように1100世帯にはいわゆる案内をさせていただいている。私たちはその子ども達の、子どもの第三の居場所事業を通じて、それが子ども家庭庁の成育環境課の方に政策として自治体を支援しますよという制度につながっていっている。
(子育て支援課長)正式名は児童育成支援拠点事業になります。
(記者)それは国が施策として取り上げたってこと。
(市長)施策として、私たちの、尾道のいわゆる日本財団から取組をしている事業そのものの中で、私たちの取組で訴えて、いわゆる厚生労働省と文部科学省という話の中で、子ども家庭庁に成育環境課という課があって、その課がさっきあった児童支援拠点事業という形で運営に対して補助しますという制度まで作っている。だから第三の居場所事業というのは、子ども達が食事もそうなんですけど、学校の活動とか、あるいは家庭的に少し課題があるような子供を預かりながら、家庭生活を安定させていくなかで、子どもたちが立ち直っていくというのが尾道の第三の居場所事業の実績なんです。それを運営していくという話になると、運営者の人件費とか、そういったようなものがいつまでも支援をいただかないとできないので、この度、家庭庁の方から支援する事業にまで発展している。国も含めて、子供たちのそういう支援をしていく仕組みにはなっている。ただ、実際にはそれだけじゃなくて、それに該当しなくてもいわゆる食事の問題に課題があるような子ども・家庭があるので、そこをこういったような形で支援していこうということで、フードパントリー制度に事業として展開していると。ですから、何パーセントとか何人とかいうような数字は持ち合わせてはいません。
(記者)これからどんなですか?増えてくる、貧困家庭は。それとも減ってくる。
(市長)増えてくる、減ってくるかは難しいですが、現実にそういった子どもとか家庭があるということですので、それを今支援している話で、これから将来的な話はちょっと難しいです。
(記者)最後ですけど、日本財団で子どもの居場所を作りましたよね。3年間は補助を出して後は市が自主運営で。
(市長)さっき言いましたように、尾道市の取組の運営をする中で、国がきっちり支援してほしいということの願いの中で、子ども家庭庁の方が事業として支援する仕組みは作った。今回はフードパントリーなので第三の居場所とは違う事業。
(記者)国の事業でまだやってないわけですね。
(市長)第三の居場所事業の中で、今の子ども家庭庁の支援事業もこれから使わせてもらうということ。
(記者)今後の展開ね。
(市長)それは国が制度としてとして作った。私たちの取組が実のあるものだと思って。
(記者)国の施策として取り上げたという事。
(市長)これはもう全く別もの
(記者)さっき1,100世帯という数が出たんですが、当面31日からの利用ですよね。申し込みはもうしていると思うのですが、どれぐらい来ていますか。
(子育て支援課長)申し込みの方は、まだ来ておりません。今、ご案内をしている状態です。
(記者)もう1週間ですけど、返答はまだ来てないということですね。
(子育て支援課長)はい。
(記者)市議会でも前に出たんですが、これは早い者勝ちになるんですかね。登録している人に取りに来てくださいっていう案内が来ると欲しい人は早く行く。それで個数制限がありますとあるので、無くなれば終わりということですか。
(社会福祉協議会)そうですね。ご質問のとおりですけれども、ただ早い者勝ちといいましても、その物品によって個数制限を付けていきますので、あるものすべてをお一人の方が持ち帰ることができないようなルールにしております。
(記者)これも市議会で出ていたのですが、やっぱり欲しい食品っていうのはみんなが欲しい傾向が強くて、欲しくないものが残る傾向にあるっていうのは言っていたんですが、その辺のバランスをどのように運用されていく予定というか計画ですかね。
(子育て支援課)そうですね。おっしゃっていただいたように、利用される方については多分欲しいもの、今であればお米であったりがたぶん望まれると思うんですが、そういったフードメイトの方の声をフードパートナーさんの方にお届けさせていただいて、希望のあるものがより集まりやすい仕組みにしていこうというふうには考えております。
【その他の質問】
(記者)尾道福屋の後に2階にカプセルホテルの入居が決定いたしました。この件についての受けとめをお聞かせください。
(市長)あの福屋の後、どのような形で展開するかということで取組をさせてもらっている中で、前回の福屋さんの場合は一括で受けられて、それに福屋さんの方がテナントを入れられて運営をされていた。今はそういった展開が非常に難しい状況だということで、それぞれフロアごとでどうするかという調整の中で、今回、地元の事業者の方が手を挙げていただいて、カプセルホテルということで、そういう意味では非常にありがたいということだと思っています。それは一つは、従来から尾道は尾道の成長産業、国も併せて、観光産業というのは成長産業にしたいという話の中で、事業者の手を挙げられている方も、そういった思いのなかで事業に協力をいただくということで、この度、カプセルホテルということだと思っています。実際、今福岡でカプセルホテルを2カ所やっている方と、昨日ちょうど話をする中で、今は従来のビジネスで使われている方が多いんですけど、今は旅行客が非常にカプセルホテルの利用率が高い。まあそういう状況で、タイミング的には非常に良い時期に開始されるんじゃないかというお声はいただいています。その後、1階、あるいは地下というところがまだ残っていますので、全体としては順次決まった段階で発表できればと思っているところです。内容的にはまだこれから関係者と協議しながら詰めていきたいということです。
(記者)一方で、市民にとってはカプセルホテルは地元の人が利用するものではないということで、1階ですとか地下に地元の人が利用できるものに入って欲しいという声がありますけど、市長として街づくりの観点からどのように捉えていますか。
(市長)市民の声とですね、ビジネスモデルになるのかということですよね。出店いただく方はビジネスにならないと出店のいわゆる契約に至らない。市民の声は伺っていますけど、その市民の声を伺った形での業種のところにはありとあらゆるチャンネルで展開していますけど、非常に厳しい。それが今の現状だと思います。逆に言いますと、一つは駐車場の問題。それから、市民の方の願いであった食品とか、そういうスーパー系の話になってくると身近な物を買える場所が欲しいという話は、それが今のビジネスモデルとして、あの立地では難しいという状況ですので、今まで私どもはそっちの意向を受けながら取組をしてきましたけど、なかなかビジネスとしての立地に向いてる状況ではないというような状況なので、それを受けながら、できるだけ市民ニーズに応えられるということを模索しながら、フロアの契約をできればしていきたいと思っているところです。
(記者)ひと月ほど前に飲酒運転の職員さんがおられましたが、その後、処分の状況とか、今調査の段階なのかもしれませんが、どのような状況になっていますでしょうか。
(市長)本人に対して、いわゆる厳正な処分をさせていただくということで、最終的な状況につきましては、今月中には市としての対応を考えている状況です。
(記者)関連しまして、その後市としてですね、綱紀粛正と言いますか、不祥事が起こらないためにどのような通達ですとか、職員への研修ですとか何かなさったことがありますでしょうか。どのような方針で臨んでおられますか。
(総務部長)まず、冒頭の御質問でございますけれども、市長の方からもございましたとおり、市の職員の懲戒指針に基づきまして対処するために、今現在、あの処分の内容について整理をしているところでございます。9月24日に発表させていただいた9月21日の飲酒運転の事例につきましては、9月25日にまず綱紀粛正の内容を各職員の方に発出をしております。また、改めて9月25日、部長級の職員に対しまして市長の方から訓示をしていただいております。併せて同日ですけれども、副市長の方からも具体的な飲酒運転撲滅に向けた管理職の取組について、部長級の方に指示をさせていただいているところでございます。また、今後につきましてはですね11月11日に交通安全の研修を現在企画をしております。また、今月ですけれども、ちょっとまだ内容が違いますけれども、管理職に対しましてモチベーションマネジメントアップの研修を10月24日、明後日ですね、実施をするような企画を現在しているところでございます。以上でございます。
(記者)色々取組をなさっているというふうにお聞きしたんですけれども、改めてお伺いするんですが、私、4月に尾道市着任をしましてですね、逮捕者がずっと出ているなというのと、まあ不祥事が続いているなという実感を持っているんですけれども、こういった不祥事が相次いでいる根本的な原因というのは、どのように市長はお考えになりますでしょうか。
(市長)基本的にはですね、個人のモラルの問題だというふうに捉えています。組織全体でそういった雰囲気醸成があるわけではございませんので、この場合、いくらいろんな形で話をしていても、本人自身がそのことを、例えば、今まであった案件、飲酒にしてもそうでございますけど、いろいろ話はしても本人の意識に届いていない。ですから厳正の処分をして戒めるということだというふうに思っています。そういう意味で言うと、非常に課題意識を持っていますけど、今回の飲酒の場合なんかは、そういう立場にいて、最後は本人が飲酒しているのは分かったうえで乗って帰る。それは絶対許すことができないことをやっているということですけど、これはもうあくまでも個人の問題だというふうに思うので、そういう意味では今後とも本人にそういう意識が根付くような形で聞かせていく研修を重ねていくということが私たちとしては責務だと思っていますので、それは今後とも続けていきたい。それでじゃあ100%かという話になるんですけど、それはめざしていきたいという思いがありますけど、そういうつもりでとにかく市民の負託に応えられる公務員として立場を認識して、信頼に応えられるということを改めて認識しながら日常の勤務に当たらすということだというふうに思います。社会通念上許されないことをあえて公務員がしてしまうということは、これは断じて許されないというふうに思っています。
(記者)元に帰るんですけど、福屋。今後、1階と地下が空いているわけで、さっきのコンセプト考えたとして、観光産業。1階と地下へ何を貼り付けるかという話ですけど、方向性としてそういう方向性目指して行くのかという話と、いつ頃までを目途に残りの2つのフロアを埋めていくのか。見通しがあれば。
(市長)ビジネスモデルに展開をしていって入っていただくというのは大切なことだと思っています。入っていただいて、そのビジネスが展開できるという業種の人を優先して入っていただく。基本的に、例えばほかの自治体でいうと、フロアは市が買って公共的な施設を入れるというようなとこまでを私たちは考えてない。ですから、基本的に尾道の持っている資源の中でビジネスがそこでできるという人たちをパートナーとして迎えてみたい。ですから、いつまでというような、なかなか日数を区切るということはできない。できるだけ早くということを想定しながら、今のように一番難しいのは地下だと思っています。ですから、あの1階の部分、2階の部分というのが先に決まれば決まった段階で地下になると思います。非常に地下というのは難しいということだと今つくづく認識しております。それから業界に関わって、近隣のところでも地下のいわゆる食品売り場は殆ど苦戦をしています。そういう全体の状況の中で、市民のニーズというのがあるのは充分承知しているのですけど、その中で本当にいろんなところにアクセスしながら、私たちも直接出店担当者と話をしてセールもしますけど、最終的には出店担当者の意向じゃなしに会社として取締役会でだめだというようなことを何回も受けておりますので、非常に厳しい環境の中で今関係者は一生懸命、ただビジネスになるかならないかということなので、それで市民ニーズに応えられるかどうかということを入れながら、どの程度のことができるかという話だと思います。
(記者)ちょっと言えないと思うのですけど、フロアごとに条件違うんだけど、家賃を変えていくっていうことは考えていますか。融通性を持たせること。
(市長)様々な方法を考えながらやっているんで何か家賃が高いから入らないとか全然そんなことはないので。
(記者)いや、最終的に今回も家賃でしょう、浦島も実態は。
(市長)家賃そのものは交渉ですので、それぞれを別々にすると言ったらまた逆に言うと、入る事業者によったら非常に差がついてくるという話は、賃料を出す側からしたら難しいので、
実際にやってみている中で、ものすごくハードルが高い。だから逆に言うと、いろんな市の公共施設の中で、いわゆるデパートとかさまざま撤退しているのを、ほとんどと言っていいぐらい、その後に入ってくる事業者を探すのが非常に厳しい状況を、どこの自治体もやっているという話なんです。だから、安直にこうやったらああやったらできるというような状況でないということはある程度知っておいていただいて、それを受けて展開をしていっている。入った事業者間同士で差があるということは、それはクレームがつきますから。
(記者)あれ、スーパーも諦めている。もう難しいから。
(市長)業種を言っているわけじゃないんで、極端に諦めたとか何とかじゃなくて、ビジネスになるかならないかということで、業種をあそこのフロアを活用して、いわゆるビジネスをやりながら、市民生活にも役立つようなことを思っている。
以上