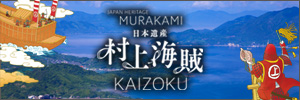本文
2024(令和6)年9月定例市長記者会見
2024(令和6)年9月定例市長記者会見
会見日:2024(令和6)年9月19日(木曜日)
会見内容
1. 令和6年度秋の文化行事について
会見録
【令和6年度秋の文化行事について】
(市長)皆様、おはようございます。今日は尾道の秋の文化行事ということで紹介させてもらいたいと思います。2013年に文化庁長官とか、尾道市を文化芸術創造都市ということで、本当に市民の皆さん、関係者の皆さんの取組で、文化芸術創造都市という名前をいただいたということでございます。その後、合併をする中で、さまざまな形で御調町の圓鍔勝三先生、あるいは平山郁夫先生ということで、合併することによって文化芸術の幅を広げることができてまいりました。また、一方、日本遺産ということの中で尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市、それから村上海賊、北前船、さまざまな形で尾道は歩みを続けてきているところでございますが、本年はとりわけ名誉市民である小林和作さんの没後50年ということで、今美術館の方では『坂道を歩く』ということで、中川一政さんとの企画展を開催させていただいているところですが、これもさまざまな形で、なかた美術館であるとか、あるいはオノテツとか、小林和作旧居であるとか、没後を記念した取組を開催させていただいています。また、浄土寺の源氏物語図扇面貼交屏風が9日間東京国立博物館にあったものが尾道に帰ってきて特別公開ということでございまして、それに合わせてロータリークラブ等が公開講座をしていただいたり、また、しまなみ江戸落語会とかN響のコンサートであるとか、様々な形で9月、11月ということで、文化行事が開催されますので、本日はそのことを皆さん方にご紹介したいと思っています。詳細につきましては担当課から説明させますので、よろしくお願いします。
(文化振興課長)この度ご紹介させていただくのは、令和6年度文化振興課関連の秋の文化行事についてです。尾道では毎年秋になると灯りまつりですとかベッチャー祭りなどさまざまな行事が行われておりますが、今年は先ほど市長が申し上げましたが、小林和作没後50年のイベントや、源氏物語扇面図屏風の尾道里帰り等、尾道の節目と言える文化行事が行われる予定となっております。皆様には行事の一覧表と各イベントのチラシをお配りしていますが、短期間の間にこれだけのイベントがあるというのは尾道ならではではないかと思いますので、この機会にぜひ多くの皆様に尾道の秋を満喫していただきたいと思います。一覧表に記載のイベントを全部ご説明する時間はありませんので、それぞれ添付のチラシを参考にしていただきたいと思いますが、主なものをいくつか簡単に紹介をさせていただきます。まず小林和作没後50年の関連イベントについてです。この度、小林和作画伯が設立に携わった尾道美術協会が創立90周年を迎えるということで、毎年開催されております大作展、こちらの方が今年はBankで開催されることになりました。また、商店街ではショーウインドーに絵画を展示する、和作忌協賛街頭展を例年通り開催するとともに、9月14日から開催されています市立美術館での特別展に関連して、小林和作ゆかりの品の一部をBankでも展示をすることにしております。さらに民間におきましても、NPO法人尾道空き家再生プロジェクトさんが小林和作旧居等で『和作ウイーク2024』と題した各種イベントを開催するなど、市内各地でさまざまな記念イベントが実施されます。文化振興課では、これらのイベントを掲載した小林和作没後50年記念マップというものを製作しまして各施設に配置しますので、旧市内に点在する和作ゆかりの地をこの機会に散策していただいて、若い世代の市民の方や観光客にも名誉市民小林和作を知っていただきたいと思っております。次に今回だけの特別行事として開催されます、浄土寺所蔵の源氏物語扇面図屏風の特別公開についてでございます。この屏風は、普段は東京国立博物館に寄託されているため、なかなか見ることができませんが、この度、尾道への里帰りが実現しまして、期間限定で特別に公開されることになりました。これを記念しまして、ロータリークラブ主催の市民公開講座の他、記念講演、また文化財講座などが開催されます。今年話題の源氏物語が描かれた美しい絵屏風につきまして、ぜひこの機会にその魅力を堪能していただければと思っております。次に日本遺産関連事業としましては、村上海賊の海城と山城15選というお城をテーマにした村上海賊巡回展を開催いたします。こちらは今治市との共催で、来週9月25日からはおのみち歴史博物館で開催されることになっております。また、巡回展とあわせましてデジタルスタンプラリーも実施する予定です。チラシの中にQRコードがありますので、このQRコードから参加登録をしていただいて市内各地にあります城跡をめぐってデジタルスタンプを集めますと、抽選で村上海賊ハンドタオルや特産品等が当たりますので、多くの皆さんにご参加していただければと思っております。最後になりますが、しまなみ交流館の催し物をご紹介いたします。9月29日日曜日にN響メンバーによる室内楽コンサート、また、11月23日土曜日にはしまなみ江戸落語会を開催いたしますので、ぜひご来場いただき、楽しいひと時をお過ごしいただきたいと思います。それでは以上で秋の主な文化行事についての説明を終わります。各イベントにつきまして、何かご質問があればお願いいたします。
(記者)西井学芸員にお伺いすることになると思いますけど、源氏物語図屏風についてですけど、里帰りは何年以来になりますか?
(文化振興課)はい。源氏物語図屏風は、浄土寺所蔵のものでございまして、平成30年に浄土寺から貸し出しをされまして、サントリー美術館、メトロポリタン美術館に回ってきて、最後、東京国立博物館で今、調査研究をしておりまして、30年度以来の6年ぶりの里帰りとなっております。
(記者)関連の講演があり、そこで学術的価値など話されると思うのですけど、チラシの裏にもありますが、この屏風の価値というのはどういったところにありますか。
(文化振興課)いろいろな価値が充分あると思いますが、屏風仕立てで扇に書かれた源氏物語ということで、いくつかは、扇に書かれたものについては日本最古ではないかというふうにいわれていることもございますので、扇が貼り交ぜられた屏風が、しっかりこれだけの形で残って、しかも美しい状態で残っているところに大きな価値があると考えておりますので、多くの皆様に是非ご覧頂ければという風に考えているところでございます。
(記者)全部でイベントは何個ありますか。
(文化振興課)一覧表に載せておりますように1から番号をふっておりますけれども、27個の行事がありまして、それとは別に小林和作没後50年で記念イベントが5つございます。32個ということになります。
(記者)何日から何日までですか。
(文化振興課)会期が最初にくるのが9月で、9月以降11月までのイベントということで掲載をしております。最初がデジタルスタンプラリーから始まって、11月23日のしまなみ江戸落語会が最後ということになります。
(記者)11月末でいいですか。
(文化振興課)そうですね。
【その他質問】
(記者)尾道市発注工事をめぐる贈収賄事件についてお伺いしたいと思います。元職員が、初公判で、2013年の土木課配属後に上司から仕事がうまくいくなら予定価格を教えてもいいと言われたと証言しました。他の職員が教えているのを見聞きしたとも証言しています。その件について、昨日閉会しました市議会でも質疑がありまして、そこでは総務部長が職員にヒアリングした結果、そういった事実はなかったという答弁がありました。この件についての市長の受け止めをお伺いしたいと思います。
(市長)職員による官製談合ということで、本当に厳しく受け止めているところでございます。この事件、あった事案そのものですね、警察が入って関係の職員も含めて調査をしたということが基本でございますので、職員がそういった事を言われているということも警察も承知の上で調べている事ですので、その中でその特定をされたという話ですから、私たち自身も警察以上のことの捜査ができるわけでございませんので、その内容を受け止めて、組織的な内容であるなら、他の職員を含めて検挙されているはずでございますので、そういった事実はないというふうに受け止めていますし、関係の職員もないので、ヒアリングもそうですし、今までこの検挙にいたるまで警察が調査しているということでございますので、組織的な対応があったというふうにはとらえておりません。以上です。
(記者)市議会では、そうは言っても市民は納得しない、第三者委員会のような外部調査が必要ではないかという意見もありました。そのことについてどう思われますか。
(市長)第三者委員会というのと、警察というのはちょっと違うと思いますから、私たちは今回、本当に市民の皆様に申し訳なかったと捉えているんですけど、警察の捜査に全面協力してまいりましたので、その内容の中で先程の逮捕に至った職員からそのような言葉を警察も聞いていますので、その内容も含めて取組をしていただいていると思っていますので、組織めいたものはなかったというふうに思っていますので、私たちの方が第三者委員会を開いたとしても、警察以上のことが出来るわけではございませんので、そのことを受け止めて今後そのようなことがないように、今日午前と午後になると思いますけど、研修をさせていただいて、信頼回復に努めていきたいというふうに思っています。以上です。
(記者)ただ、公判でこういった証言があったということで市民はやはり疑いの目を持っていると思われます。そこで、市民に対する名誉毀損であるという思いはないですか。つまり、この被告に対して名誉毀損で訴える必要があるといった考えはありませんか。
(市長)私も裁判で証人ということで立ち会った事がございますけど、きちんと嘘でないということを宣誓して対応しますので、職員の方はそういうことで対応しているわけではございませんので、自分のそれぞれの考えたことを述べたというふうに思っていますけど、それは今回の捜査の過程の中でも、そういった発言ということがあって、それに合わせて警察が職員の側に全部聴取をしていますので、その中で個人の検挙に立っているということでございますので、その職員がその名誉毀損というようなところまでは、今のところは考えてないということです。
(記者)研修につきましてですけれども、先ほど市長から信頼回復に努めていく一つであろうということでございました。改めまして、この研修につきまして、市の職員にどのように学んでもらいたいといいますか、意義であるとか、どのようにお考えでございましょうか。
(市長)基本的に、市の職員というのは公務員ですので、全体の奉仕者として市民に信頼を得る行動をしないといけないということが勤務の大前提だというふうに思いますから、その内容に逸脱するようなことがあったということが非常に残念なことで、組織の中でも従来からその事を徹底して取り組んでいる中でこのようなことが起こっているということに対して本当に重く受け止めているところです。基本的には今までも職員にそういった取組を徹底しているつもりであっても、あるいは飲酒の運転であったり、非常に残念なことがあったということも改めて受け止めて、引き続き繰り返し繰り返し取組が信頼できる行動になるように取り組んでいく、継続して研修等日常的な取組で徹底していくということを繰り返していくしかないと思っているところです。
(記者)改めましての再発防止策ということで、一つ今回の研修があったということ。あと、以前の会見でシステムの方にも何か新たに加えるというようなことの考えがございましたけれども、その再発防止策のほうはありますでしょうか。
(市長)はい。それにつきましては担当の部長の方から説明させます。
(建設部長)再発防止につきましては今、研修ということもありましたが、契約のやり方自体を、入札のやり方自体を変えていきたいと思っております。具体的に今検討しておりますのは、入札を行う際に最低制限価格というのを設定するのですが、これにランダム係数をかけて、最低制限価格が誰にもわからないというようにすることを今考えております。このことについては今検討中ですが、できるだけ早く実施できるように取り組んでいるところでございます。以上です。
(記者)事務的なことで恐縮ですが、誰にもわからないというのは、それは誰を指すのでしょうか。市の職員も含めてということでしょうか。
(建設部長)市の職員も含めて業者にもわからないということを考えております。
(記者)建設部長に聞きたいんですけど、かつては入札予定価格と最低制限価格ですかね、100と70と非常にわかりやすい構図で入札が行われていたんですけど、公共事業がだんだん減ってきて、予定価格はいいんですけど最低制限価格の方が今90の上ぐらいですかね、その入札制度の変更というか手直しが、昔は要するに談合があったり汚職があったんですけど、非常に分かりにくい。その一方、他の自治体では入札予定価格を、入札をする前に公表するようなそういう自治体もありますよね。その辺の入札制度のシステムのあり方と、今回の汚職の関わり、どういう関わりがあったかどうかわかりませんけど、その辺はどういうふうに見ておられますか。要は最低制限価格がかなり90過ぎぐらいまで上積みされている。かつての100と75の入札制度から変わってきている。そういう流れと今回の汚職との関連は多少あるのですか、ないのですか。
(建設部長)最低制限価格と入札制度について今回の事件と関係があるかというと、関係ないと思っています。以前はおっしゃるように最低制限価格は75%ぐらいでしたが、入札制度がどんどん変わってきまして、今現在は92%前後だと思っています。それはダンピングの防止とか、不当に低い価格でとると下請けへの影響とかそういう事がありますので、入札制度がどんどん変わってきて、現在の価格になっているということでございます。
(記者)建設の受注業者ですね、建設土木。ある程度建設市場が受注金額をはじき出すだけの能力を持った業者がかなり増えいてる。ほぼわかるんじゃないかっていう気がするんですよね、入札の札の入れ方を見ていたら。もう思い切って、最低制限価格も入札予定価格も全部、当初から公表してそこでやるっていうようなやり方もありえるんですか、ないですか。
(建設部長)予定価格を公表している所はたくさんあると思います。最低制限価格を公表しているところはございません。ただ、最低制限価格を算出する式は、尾道市も公表しております。また、業者のパソコンで使っている積算システムの精度も上がっておりますし、資材や人件費等も公表しておりますので、予定価格というのは以前に比べてはじける、同じ価格がはじける可能性は高いと思っております。今回予定価格までの公表に至らなかったのは、やはり国の流れが予定価格というのは、事後公表にすべきということで通達というか、方針が出ておりますので、それに従いまして、尾道市は予定価格の公表は行わず、最低制限価格にランダム係数をかけるということで検討しているということでございます。
(記者)今の入札制度をそのままこれからも継続していくということになるわけですね。
(建設部長)ですから最低制限価格にランダム係数をかけるということで、入札制度につきましては、変えていこうということで今検討しているところでございます。
(市長)入札制度の中で非常に難しいというのもあるんですけど、例えばこの庁舎ですよね。この庁舎は当時完成したのが、令和元年の12月に竣工ですけど、予定価格を公表せず取組をさせてもらった。その時に福山は総合体育館、そして三原は庁舎、それらは予定価格を皆公表した入札になっています。そして、ここの庁舎そのものは、今の施工していただいた清水建設のJVを組んでいただいて、27%を安く入ってもらったということがありますので、その予定価格そのものの扱いをどうするかというのは時代の流れもあるんですけど、市にとってメリットがあるかないかとか、その辺の事も念頭に置かないと、何かする何かするみたいな話では、なかなか一様にですね、ハードルを決めてしまうということがいかがなものかということになるわけです。今回のように大阪万博など資材高騰とかいう話になると、その価格ではもう全く業者が手を挙げてこないという話にもなるので、非常にいろいろさまざまな事案を考えながら、検討していかなければならない。ただ、今回あったような官製談合というのは、あくまでそれを防ぐということの手立てを考えていくということは大切なことだと思いますが、最も大切なことは、今の携わっている人の意識が、そういった談合の意識に持っていくかどうかというのが最もいけないことで、そこは厳しく、人としての公務員としてのあり方を厳しく律していかないといけない部分だと思いますけど、入札制度そのものについての多様な幅を持たせた取組がこれから求められてくるように思っています。ただ、適正なものをしっかりしていくことは当然ですけど、逆に安く入ってくることを防ぐという。
(記者)ここの市役所の場合は、清水建設がものすごい安く入りましたね。札を入れた後で安すぎたということで、それを検討した、低価格入札みたいなので。もう一つ言えば福山市の体育館、これはもう入札予定価格に近いような額を入れていましたよね。90なんぼで。
(市長)だから入札する時、どういった方法で、相手との関係も含めたときということがあるので、市の立場としたら、きちっとした建物をより安くやっていただくのがいいのが、市民にとってはいいわけですから。そうすると、例えば民間の事業でも、今回でもそうだと思うのですけど、瀬戸田のある案件事業はものすごく安く業者が入ってくれていますから、それは逆に言うと、これだけ資材が高騰してうんぬんのような話なんだけど、本当に施工する側としては必ずやらないといけない、それは自分たちの会社のメリットになる話になると、そうなるんで。入札そのものという話になると、そういったものも含めて、知恵を出して、より有利により素晴らしいものにするということが求められている側面もありますよ。だから、そこを念頭に入れながら、今回の事案が再発することがないようにするのは、人の問題なので、そこは厳しく律して行くような、研修をするっていうことは当然なんですけど。今のランダムを入れてしまう事がいいのか悪いのかも含めて、しっかり検討もして対応して行きたいと思います。
(記者)今の最低制限価格のあり様は柔軟性があるんですね。柔軟性があるっていうのは極論すれば前みたいな75%切ったらもう即ダメとかではなく、多少の柔軟性というか、安くなっても高くなってもみたいなところがあるんですか。
(建設部長)最低制限価格ですが、尾道市においては、ある一定金額以上の入札につきましては、最低制限価格ではなしに調査基準額ということにしまして、調査基準額よりも低くても業者がしっかりと工事をできるということを確認できたら、その業者と契約するという方法をとっております。なので、最低制限価格と、調査基準額の違いはそこであります。
(記者)先ほどのランダム係数をかけるという話でございましたが、そのランダム係数をかけた後の数字というのは開札するまで分からないということでしょうか。
(建設部長)ランダム係数をかけるタイミングですが、今考えておりますのは、業者が入札した後にランダム係数をかけるという方向で検討しているところでございます。
(記者)官製談合をなさった高橋被告の処分のタイミングについて改めてお伺いするんですが、公判に入る前に処分をされたということだったと思います。その後、証言の中で、仕事が上手くいくならば、予定価格を教えてもいいというふうな証言が出てきて、それを聞いた時に、私は個人的にやはりその処分のタイミングが早かったのではないかというふうに思っています。といいますのは、他の自治体の方では、こういった談合事件など、犯罪とか起こした職員に対して一定の警察の調査を経て警察の起訴を経て、ある程度その判決が出た段階で懲戒処分という、容疑なり、罪の内容がある程度確定した段階で、処分という風にするのが多いように見受けているんですけれども、今回公判の前に処分されたということですね、受けた印象としてはなんとなくトカゲのしっぽ切りではないんですが、市の仕事のやり方を知っている職員が罪を問われてその公判で喋る前に処分してしまおうというようなことも考えられなくもないという印象を受けたんですが、その点について処分のタイミングについて、あらためて市長から、受け止め、こういう方針で処分したということをおっしゃって頂けますか。
(市長)詳細について一番詳しい総務部長に、判断は当然最終的に私がしましたので説明をさせます。
(総務部長)処分の時期がどうかというご質問でございますけれども、この逮捕事案がありまして、私どもも警察のほうに協力をさせて頂いております。ご承知の通り、家宅捜索の方も市役所の方に入りました。拘留を受けておりました職員には接見がかなわないということもございまして、職員の方が拘留を解かれて釈放になりまして、ただ拘留期間中も色々取り調べ等がありましたので、職員の心身の状態を確保するというような面もあって、少し時間をおいてですね、元職員の状況がどうなのかということを確認して、こちらのヒアリングに耐えられるかどうかと言うことも勘案をして、その時期を見極めて、元職員の方にはヒアリングを行いました。で、その時点で報道されておりました起訴事実について全て全面的に、本人が認めたということでございます。本人が認めずに公判にかけるというような状況でありましたら私どもなかなか処分はできませんけれども、尾道市の職員の懲戒指針に関する指針がございますが、それに照らし合わせてですね、こういった事案だけではなくて、飲酒運転等につきましても、すべて速やかに職員の処分については執り行うというような方針を持っております。で、起訴事実を全面的に認めたと言うことで、再度うちの方もこの事実に間違いはないかと言うことで、職員の方に確認をとりまして固まったということで、その指針に基づいて処分を行っております。この度だけが早いわけではなくてですね、飲酒運転等の事案に対しましても、その事実を認められた段階で判決を持たずに処分をしているところでございます。以上でございます。
(記者)繰り返しの質問で申し訳ないですけれども、着任時に上司から云々っていう高橋被告の話なんですけれども、そもそも市長、この高橋被告がなんでこういうこと言ってるのかっていうのを思われますか。なぜこういうことを言うのだろう。
(市長)なぜそんなことを言うのかとは。
(記者)要するに思いつきで言ってるのか、あるいは妄想で言ってるのか。
(市長)いや、それはコメントは控えさせてください。相手もあることですので。ただ言ったことは事実として受け止めていますけど、その内容をもって尾道市の今の組織の中には全くないと思っています。といいますのは、今回逮捕に至る前に数人の職員が全部同じように警察の方から取り調べを受けているような状況でございますし、そういう中での今回の逮捕に至っているということですから、組織的なものはあるというふうに思っていませんので、個人の判断、そしてそれで個人がそのように述べたという話ですので、そのことをとやかく言うことを今の段階で思ってないということです。
(記者)総務経済委員会の中でも出てきたのですけれども、この被告の方の入札制度への理解が低いという、そういう話があったのですが、総務部長でいいんですが、もうちょっと説明いただけますか。
(総務部長)公判の内容につきましては、職員課の職員がその公判、8月13日の公判を聞いております。その中で入札に係る事項を質問されたということでございます。その時に元職員が、その問いに対してしっかり答えられなかったというようなことがございます。具体的には入札に係る事務についてどういうやり方があるのかというような質問も多分出されたというふうに聞いておりますけれども、それに対してはご自分の口から証言をされるのではなくて、市のホームページの方に載っていますというような回答をされたと言うことは伺っております。本来、こういった事件を起こされて、その入札に係る談合等の事案を起こしたような場合ですね、どういった入札に係る手続があるとか、予定価格や最低制限価格の取り扱いがどうなるかということが具体的にその職員の方から話が公判の中でなかったということでございますので、どこまでこの入札に係る認識がその職員にあったのかというようなところで、総務経済委員会で答弁をさせて頂いたというような状況でございます。
(記者)先ほど警察が取り調べても結局誰もいなかったので、組織的なことは全くないとおっしゃいましたが、警察とかはですね、その起訴にまで持ち込めるかとか、公判維持できるかということで、かなり厳しいことでしか逮捕したりできないと思うんですけれど、例えばこの組織にですね、そういう何か風潮、人が大切だというようなことをおっしゃったと思うんですけど、そういう風潮があるかないかを見るためにも、例えば無記名でアンケートをとって、そういう過去にいた職員も含めてアンケートをとるなどして、そういう風潮という、捕まりにくい、警察沙汰にはならないけれど、市の不利益になるようなことがなかったというような調査をするお気持ちというのはございますでしょうか。
(市長)今の段階で私どもがそういったアンケートをとった職員ですね。もうすでにヒアリングもしながら確認をして取組をしていますので、そういったアンケートをとって、何とかというようなことはまったく思っていません。またそういう形で職員も疑った形で何とかしようというようなことも思っていませんし、今回のことは誠に残念なことだというふうに思いますし、当然そういった組織的な風潮があるということを感じれば、当然今の勤務している職員も含めてですね、そういったことがあるなら、対応しなければいけません。そういったことがあると思っていませんので、今やっている取組について研修を重ねていきながら、信頼できるあり方にもっていきたいと、そのように考えています。
(記者)ヒアリングという話でございましたが、ヒアリングというのは対面ですので、誰が何を言ったかっていうのが分かるので、本当のことが言いにくい人もいるのではないかと思うのですが。
(市長)そのようなことは決してないと思っていますので、今のように無記名で書いてうんぬんとかいうような話は今は思っていません。
(記者)研修の話ですけれども、そういった風潮ですね、予定価格を教えてしまった、するっと教えてしまったというような風潮が高橋被告にあったとしたらですね、それを防止するために、今回研修をやっているかと思うのですけれども、その組織としてその研修体制はこれまでこの談合防止に関する研修というのは毎年やっていたのか、それとも今回、この事件を受けて初めてこういう研修をやったのか、そこはどうでしょうか。
(建設部長)今回の研修を毎年というと私の記憶にはないのですが、今回初めてでは当然ありません。毎年というか、何年かに一回は必ずこういった研修は行っております。また、それ以外にも、コンプライアンスに関する研修も行っておりますので、こういった研修は今後も再発防止に向けて、毎年これからはやっていく必要があるのかなと思っております。
以上